
国内外のDX先進事例の紹介に加えて 今年話題となったAIの進化やDX人材育成までを網羅
#DX白書2023
大きな反響をいただいた「#DX白書2022」を大幅にアップデートし、ディズニー等のDXの次に進もうとしている企業の先進事例やそれらを取り巻くAI/Web3などのDXトレンド紹介、そしてDXを推進するための人材戦略まで、検討のヒントになる情報を多数詰め込んだ内容となっております。

国内外のDX先進事例の紹介に加えて 今年話題となったAIの進化やDX人材育成までを網羅
#DX白書2023
大きな反響をいただいた「#DX白書2022」を大幅にアップデートし、ディズニー等のDXの次に進もうとしている企業の先進事例やそれらを取り巻くAI/Web3などのDXトレンド紹介、そしてDXを推進するための人材戦略まで、検討のヒントになる情報を多数詰め込んだ内容となっております。

TikTokに興味はあるもののどうすればいいかわからない方
縦型動画を試してみたいけど、アサイン、ディレクションに対してノウハウが無い方
一度は試してみたけど、成果が出ず伸び 悩んでいる方
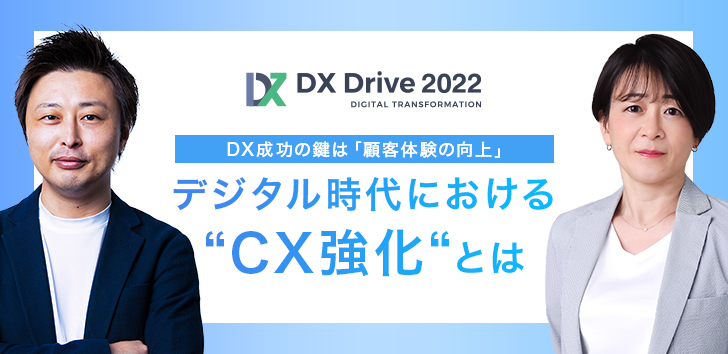
DX推進のご担当者、事業責任者の方
新規事業や組織改革を担う事業責任者の方
マーケティング担当、Web担当の方

著者: Kaizen 編集部

顧客体験DXで企業課題をカイゼンするKaizen Platformが、各業界のDXの実践者をゲストに迎え、オンライン開催する「DX Drive」。
「日本のDXを加速する。」をコンセプトに、毎回、DXに関連する注目のテーマをピックアップ。ゲストと共にDXの"今"と"リアリティ"を届けるイベントです。
株式会社ギークプラスと、エンSX株式会社の担当者の方をお迎えし、Kaizen Platform代表の須藤憲司が、「TheModelに頼らないBtoBマーケの実践知」について深掘りしました。
本記事では、2025年6月24日(火)に開催されたイベントの内容をお伝えします。

講演者
株式会社ギークプラス
経営管理部 部長 マーケティングG GM
夏 在樹リクルートやGOなど複数社で事業初期から拡大フェーズのBtoBマーケティングに従事。現在は物流現場の自動化を支援するギークプラスで経営管理・マーケティング・PRを横断的に統括し、複数事業の成長戦略の実行を牽引。
エンSX株式会社
事業責任者
野田 勇次郎2016年、エン・ジャパン株式会社に新卒入社。 最速でチームリーダー、マネージャーを経験し、 全社ギネスの記録更新や 何度も全社表彰を受賞(殿堂入り)。 その後、SaaS領域やWebサイトUI・UXなどの 新規事業の立ち上げに営業責任者として携わり、 複数の事業立ち上げを経験。 2022年からは、事業責任者として「エンSX事業」の 立上げに従事、事業を牽引している。
株式会社Kaizen Platform
代表取締役
須藤 憲司2003年に早稲田大学を卒業後、リクルートに入社。同社のマーケティング部門、新規事業開発部門を経て、リクルートマーケティングパートナーズ執行役員として活躍。その後、2013年にKaizen Platformを米国で創業。現在は日米2拠点で事業を展開。企業のDXを支援する「KAIZEN DX」、Webサービスやモバイルや動画広告などのUI/UX改善をする「KAIZEN UX」を提供。
ーまずは今回のテーマ「エンタープライズ攻略最前線 TheModelに頼らないBtoBマーケの実践知」について、須藤さんより解説いただきます。
須藤:BtoBマーケティングと一口に言っても、その対象は中小企業から大手企業まで幅広く存在しています。中でも、エンタープライズ(大手企業)との取引が持つインパクトは圧倒的です。
まず注目すべきは、1社あたりの契約単価の高さです。中小企業と比べて、契約単価や投資予算は数十倍、数百倍、場合によっては数千倍にもなります。つまり、大企業と1社取引するだけで得られるビジネスインパクトが、まったく違うんです。
加えて、最近はDXやAIへの投資も非常に活発で、関連予算は今も拡大傾向にあります。さらに、大手企業は組織が横断的に構成されているため、アップセルのチャンスも多く、一度導入されれば他部門やグループ会社に展開されていくケースも少なくありません。

また、大手企業との取引は信頼性の証明にもなります。その後の他社営業にも良い影響をもたらし、営業効率が飛躍的に向上するといった、ネットワーク効果も期待できます。
ここで最初にお伝えしたいのは、日本の企業全体における大企業の割合はわずか0.3%ということ。しかしこの0.3%の大企業が、ソフトウェアやIT、DX関連の投資の約8割を占めているんです。つまり、1社あたりの投資金額で見ると、中小企業の約1300倍。それだけインパクトが大きいということになります。逆に言えば、中小企業を1社取るのと、大企業を1社取るのとでは、1300倍の価値の違いがあるとも言えるでしょう。
実際、私たちKaizen Platformでもエンタープライズ領域に注力しており、売上の約50%は上位20社、約80%は上位50社によって構成されているというのが現状です。
では次に、いわゆるBtoBマーケティングの代表的なフレームワーク「The Model」について触れていきたいと思います。
Salesforceが提唱した「The Model」は、特に中小企業(いわゆるSMB)を対象とした戦略として非常に有名です。ただし、このSMB向けのアプローチと、大企業(エンタープライズ)を攻略するアプローチとでは、根本的に異なる点がいくつもあります。
一つ目は、リードの獲得や扱い方の違いです。中小企業を対象とする場合は、とにかく多くのリードを集めて、そこからスクリーニングを重ねて商談数を増やしていく、というやり方が一般的です。一方で、エンタープライズでは、特定のアカウントを一社ずつ狙い撃ちしていくスタイルが求められます。アプローチの仕方そのものが異なるのです。
二つ目は、体制の違いです。The Model型の営業体制では、マーケティング → インサイドセールス(IS) → フィールドセールス(FS)というように、役割ごとに分業しながらバトンを渡していく流れになります。しかし、エンタープライズ営業においては、それぞれの役割を統括し、状況を俯瞰して判断できる“司令塔”のような存在が不可欠になります。分業だけでは複雑な意思決定プロセスに対応しきれないためです。
三つ目は、コンテンツの設計です。中小企業向けには、汎用的なホワイトペーパーや営業資料でもある程度対応できますが、エンタープライズ向けには、業界ごとに特化した資料や、場合によっては個社ごとのカスタマイズ提案が求められます。情報の解像度や対応力が問われる領域です。
そして四つ目は、KPIの設計です。SMBでは、短期的な成果が重視されます。リード獲得から商談、受注、さらには早期の黒字化までを短いスパンで目指す傾向にあります。一方で、エンタープライズの場合は、年間予算の枠組みの中でどう提案を組み込んでもらうかが重要になります。したがって、数ヶ月単位で成果を求めるのではなく、より中長期的な視点が必要になります。
このように、同じBtoBマーケティングといっても、SMBとエンタープライズでは前提も進め方も大きく異なります。それぞれに応じた戦略設計が求められるということです。
このとき、マーケターが考えるべきことについても触れておきたいと思います。
いわゆる「The Model」と呼ばれる手法と、エンタープライズ向けの営業で用いられる「アカウントベースドマーケティング(ABM)」では、アプローチの考え方が大きく異なります。
The Modelでは、いわゆる“ファネル”、つまり上から下に向かって徐々に絞り込んでいくようなイメージで、リードを管理・育成していくのが一般的です。
一方、ABMでは、顧客との接点ができた後に、そこからどうやって接点を拡大していくか、どう深掘りしていくかが重要になります。たとえば、意思決定のプロセスをどう捉えるか、あるいはお客様の予算の中でどれだけシェアを拡大していけるか、といった視点が求められます。
ーここからは、ISから見たエンタープライズ攻略の本質について、エンSXさまの事例をご紹介いただきます。
野田:エンSX株式会社は、エン・ジャパン株式会社の子会社として、2024年4月に立ち上がった会社で、ちょうど1年あまりが経過したところです。
もともとは、社内の「内販部隊」としてスタートしました。エン・ジャパンの中には複数のグループや事業がありますが、その中で、BtoBマーケティングや営業支援を担うIS部門を、横断的に構築していく取り組みを行っていました。
その後、いわゆる「外販」のビジネスにもチャレンジし、現在は、外部の企業様向けにISの代行やマーケティング支援なども提供しています。現在は、この“内販”と“外販”の二軸を柱とした事業展開をしています。

ISの部隊は社内に抱えていますが、営業メンバーという特性上、どうしても離職が発生しやすいという課題がエン・ジャパンの中で以前からありました。そこで、子会社として切り出すことで、離職率を抑え、リテンションを高めるとともに、報酬制度の整備によって、営業力のある人材が長く働ける環境をつくる——そんな構想のもとで、現在の事業がスタートしました。
現在は、ISの代行だけでなく、さらに幅広い支援を行っています。たとえば、今日のテーマでもあるアカウントベースでの攻略プランの設計支援や、その実行フェーズの伴走。また、「商談が進まない」「クロージングがうまくいかない」「ヒアリングが弱い」といった営業課題に対しては、トレーニングまで含めた支援も行っており、かなり多岐にわたるサービスを提供している会社です。

須藤:実は私たちKaizen Platformも、野田さんたちエンSXの皆さんにお世話になっています。
世の中には、いわゆる“営業代行会社”がたくさんありますが、共通して課題になるのが「離職率の高さ」です。これは、私たちにとっても非常に大きな悩みのひとつです。
特にエンタープライズセールスは、1社を攻略するまでにどうしても時間がかかりますし、商品知識や業界理解といったノウハウを習得するにも一定の時間が必要です。だからこそ、体制の安定性はとても重要になります。
その点、エンSXさんのように離職率が低く、腰を据えて取り組んでくださるチームがあるというのは、私たちにとって非常に心強い、圧倒的にありがたい存在だと感じています。
須藤:では、最初のテーマに入りたいと思います。「エンタープライズ攻略におけるISが果たす役割とは?」という問いです。
野田:いろんな考え方があるとは思いますが、私自身が強く感じているのは、「The Model型」のISとは違って、よりFSに近い役割が求められる、という点です。
たとえば、ISであっても、競合のIR情報を調べる、業界のトレンドを把握する、攻略対象企業のグループ会社を調べる、組織図を描いてアカウントプランを設計する――こうした活動が必要になるケースが多くあります。
通常のIS業務ではあまり踏み込まない領域かもしれませんが、エンタープライズでは1社のインパクトが非常に大きいため、こうした深い情報収集や戦略設計まで含めて取り組む必要があると感じています。
なぜそこまでやる必要があるのかというと、やはり大企業では単価が高く、いわゆる“パッケージ型”の提案が通用しにくいからです。僕の感覚では、大企業ほどオーダーメイドを好む傾向が強く、営業の攻略難易度は非常に高いと思っています。
その理由は大きく二つあります。一つ目は、意思決定構造が非常に複雑であること。最近の事例でも、担当者と話していた内容と、その上の部長や執行役員のニーズがまったく異なっていたり、気づけば隣の部門の人が関与してきて、さらに別のニーズが出てくるといったケースがありました。こうなると、シンプルなセールスアプローチでは対応が難しくなります。
二つ目は、オペレーション上の制約です。数百人~数千人規模の大企業では、業務オペレーションがすでに固まっていることが多く、そこに汎用的なソリューションをそのまま当て込むのは非常に難しい。結果として、FSの難易度も高くなっています。だからこそ、ISもその前提に合わせて役割を拡張していく必要がある。私としては、ISにもより高度な情報収集力や戦略設計力が求められている、というイメージを持っています。
須藤:続いてのテーマです。「従来のISと、今求められるスキルセットの違いとは?」という点について、お話を伺っていきたいと思います。
野田:ここは先ほどの話の延長線上になるかもしれませんが、やはり現在求められるスキルセットには、従来型とは明確な違いがあると思っています。
従来の「The Model」型ISでは、アポイントの獲得数や活動量といった“量の指標”が評価の中心でした。ですが、現在ではそれだけでは通用しない場面が増えてきていると感じています。
特に今重要なのは、「相談ができるIS」としてのスキルです。汎用的なソリューションでは通じないケースが多い中で、「この課題にはこういうアプローチが必要だ」と自分で判断し、さらに「このアカウントの未来像をこう描いて、それに合わせて提案を組み立てていく」といった力が必要になってきています。
つまり、お客様との間でしっかりとした対話を重ねたり、FSが行うような“ラスト1マイル”のトーク、本音や悩みに踏み込むようなリアルな対話を、IS自身がある程度担えるようになっていないと、本質的な課題には入り込めないんです。
私は社内でもよく話しているのですが、最終的には「自分でFSができる」レベルまで、ISのスキルを引き上げていってほしいと思っています。
もちろん、アポイントの獲得はISの大切な役割ですし、KPIとしても設定されています。ただ、実際に良質な商談が生まれるかどうかは、やはり「お客様の情報をどれだけ理解しているか」にかかっています。
そしてそれに対して、「この課題に対しては、こういう解決策をご提案できます」といった、具体的な会話ができるかどうか。そこが、ISに求められる“本質的な価値”だと思っています。

須藤:次のテーマは「マーケティングやFSとの連携で必要な仕組みとは?」です。
野田:これがあれば完璧、というような理想の仕組みは、正直まだ私たちの中でも完成していないのですが、私自身が強く意識しているのは、FSとISを“二人三脚”で進めていく、というイメージです。そして、これはマーケティングにも同じことが言えると思っています。
実際、多くの企業では、FSとISがどれだけ顧客理解を深めていても、マーケティング部門だけが分断されてしまっている、というケースが少なくありません。
そうした中で、私たちが実践しているのは、マーケティング・IS・FSの3部門を「ひとつのチーム」として動かすことです。つまり、ひとつのプロジェクトを3者で一体となって推進していくための“場”を、あらかじめ設計しておくことを意識しています。
たとえば私たちの場合、ISが作成したアカウントプランをチーム全員で共有し、そこにフィードバックを出し合う。また、FSとISの定例ミーティングにもマーケティングが参加し、「お客様が実際にどう感じているのか」「キーマンはどの部門にいるのか」といった情報を、リアルタイムで共有できるようにしています。
こうした仕組みがないと、実際に現場で起きやすい、あるいはこれまで私たちの中でも起きていた“すれ違い”がいくつかあります。
たとえば、3部門がバラバラに動いていると、業界ごとの違いに気づかないままコンテンツを作ってしまうことがあります。私たちは人材業界に関わることが多いのですが、人材業界では採用部門を「人材開発部」と呼ぶことが一般的です。一方で、たとえば食品業界では、同じような機能を持つ部署が「健康経営推進部」など、まったく違う名称になっているケースがあります。
この違いを把握しないまま、「人事向け」として一律のコンテンツを制作してしまうと、当然ながら刺さりません。これは、冒頭でお話ししたように「汎用的なコンテンツでは通用しない」典型的な例です。
だからこそ、マーケティングも含めた三位一体の体制が必要であり、その中でマーケティングが“ハブ”のような役割を担うべきだと考えています。

また、FSとISの連携も非常に重要です。最近では、トップセールスの方が個人の力でお客様への提案をうまく進めているようなケースもありますが、その際に「この業界、たとえばEC業界ではこういった課題に対してこういうアプローチが有効だった」といったナレッジを、しっかりタイムリーに共有し、それを他の案件にも展開していく。そうした実践につながる仕組みを整えることが、今後ますます大切になっていくと感じています。
僕自身も、まさにいま「マーケ・IS・FSの三位一体体制」を意識して整えながら、日々取り組んでいるところです。
ーここからは、実際にエンタープライズ向けのマーケティング戦略を実行し、成果を出された事例として、ギークプラス様の取り組みをご紹介します。物流領域でのDX推進を背景に、さまざまな施策を組み合わせて成果を創出した事例です。
夏:はじめに、簡単に事業概要をご説明させていただきます。
昨今、「少子高齢化」や「2024年問題」などの社会課題により、「人がいない」といった声をよく耳にするようになってきました。実際、現場レベルでは必要な人材がなかなか採用できず、深刻な人手不足に直面している企業が非常に多く存在しています。
しかし、物流は止めることができない。そうしたプレッシャーの中で、日々苦慮されている企業が多いのが現状です。
私たちは、そうした課題に対して「倉庫内のオペレーションを自動化する」ことで、業務の省人化・効率化を実現し、人手不足を解消する物流ソリューションを提供している会社です。
具体的なイメージを持っていただきやすいように、ここで当社プロダクトの紹介動画をご覧いただければと思います。
私たちのプロダクトは、倉庫内での“移動距離”を削減することにより、生産性を高める、まさにDXのコンセプトを体現したソリューションです。
.jpg?width=1000&height=667&name=YSK_064%20(1).jpg)
さて、ここからは本題でもある事例のお話に移らせていただきます。
先ほどの私の話だけを聞いていると、スムーズに進んできたように見えたかもしれませんが、実は半年前まで、まったく違う状況にありました。
当時、私たちは非常に大きな事業課題を抱えていたんです。その中でも特に大きな壁だったのが、「顧客獲得」でした。というのも、それまでの顧客獲得の多くは、経営陣の人脈を通じたリファラル(紹介)によるもの。つまり、トップセールスでなんとか受注しているような状態だったんですね。
ところが、「ここからさらに事業を成長させていきたい」となったとき、このやり方だけでは限界がある。リファラルに頼っているだけでは、売上を継続的に積み上げていくことができない――。それが、当時私たちが直面していた最大の課題でした。
さらに言えば、当時のマーケティング部門は私ひとりだけ。「いよいよマーケティングを立ち上げよう」と思っても、一人でできることにはやはり限界があり、正直、かなり苦しい時期もありました。
そんな中、Kaizen Platformさんに声をかけていただき、「一緒に取り組んでいきましょう」とチームを組むことになったんです。これが、今回の取り組みの出発点になります。
そこから議論を重ねていく中で整理したのが、こちらの資料になります。
実際にどんなアプローチを取ったのかという点についてお話しします。結論から言うと、私たちが最初に取り組んだのは「顧客をきちんと理解すること」でした。
というのも、当時の私たちは、エンタープライズのお客様の中で“誰に”自社のプロダクトを提供しているのか、その解像度がまったく足りていなかったんです。それが不明瞭なまま施策を打っても、やはり施策自体のクオリティが下がってしまう。だからこそ、まずは“顧客理解”から丁寧に始めようと決めて、プロジェクトをスタートしました。
そのプロセスの中で、徐々に明確なペルソナが見えるようになってきました。そして、見えてきたペルソナに対して「どんな施策がより刺さるのか?」を検証しながら、ひとつひとつステップを踏んで進めていった形です。
まず取り組んだのが、「顧客理解を深める」というステップです。ここでは、実際にどんなアプローチをしたのかを少しご紹介させていただきます。
やったこと自体は非常にシンプルです。新規と既存を含めて10社のお客様に対し、いわゆるN=1のインタビューを実施しました。
その中で明らかになったことを、左側の図を用いてご説明します。私たちの製品は、比較的“ハイエンド”な価格帯に位置する商品です。そのため、一定の投資余力がなければ、そもそも導入の意思決定に踏み出すことが難しい、という現実があることが見えてきました。
図の左側に記載している「FCF」は、「フリーキャッシュフロー(Free Cash Flow)」を指します。このフリーキャッシュフローがある程度確保されていない企業にとっては、私たちのようなプロダクトはどうしても導入のハードルが高くなってしまう。
実際にお客様と対話する中で、この点が非常にクリアに見えてきたことは、大きな学びとなりました。
もうひとつ、重要な気づきがありました。図には「売上規模」と記載されていますが、より正確には「売上成長」と言い換えたほうが実態に近いと感じています。というのも、売上が伸びている企業というのは、物流の観点から見ると、納品すべき“モノ”の量が確実に増えていくことを意味します。
そして、取り扱う物量が増えれば増えるほど、物流に関する課題も比例して増えていく。その課題が顕在化するタイミングで、私たちのようなソリューションが必要とされるのです。
この「物流課題の顕在化 → ソリューション需要の発生」という流れが、私たちにとっては受注に直結する重要な循環であることが、今回の取り組みの中で見えてきました。
つまり、フリーキャッシュフローを一定以上確保しており、かつ売上が成長している企業こそが、私たちのプロダクトと最も親和性の高いターゲットである、ということを、N=1インタビューを通じて明確に把握することができました。
夏:こちらの資料は、今お話しした内容をもう少しブレイクダウンして整理したものになります。
私たちのように一定の金額規模となるプロダクトが、企業の中でどのような順番で検討され、どのタイミングで「導入しよう」という意思決定に至るのか。その流れを整理したのが、この図です。
図の左側から順にご説明します。まず、経営層が重視するのは、「どれだけ売上を上げるか」「どのくらい投資するか」「どれだけ利益を出すか」といった、事業の根幹に関わる論点です。
その中で、売上拡大を図るためには、まず営業やマーケティングの取り組みによって“プロフィット”をつくっていく必要があります。次に、その売上目標を実現するための「製品開発」の検討が行われ、最終的に「その製品をどう届けるか」。すなわち“デリバリー”に関する議論へとつながっていきます。
私たちが提供しているプロダクトは、この“デリバリー”に関する部分に位置づけられます。そのため、社内での意思決定の中では、比較的後半のフェーズで検討される傾向にあります。だからこそ、私たちが「どのタイミングで提案を持ち込むべきか」をきちんと理解しておくことが、非常に重要になります。
実際に検討が進む中で、ある段階になると「物流企画部門」の方々が前面に出てくるタイミングが訪れます。この部門が本格的にプロジェクト検討を開始するのが、図の中央あたりのフェーズです。
この時点でよく議題に上がるのが、たとえば「倉庫スペックは荷量に対して足りているか」「在庫をどこの倉庫に配置すべきか」といった内容です。さらに踏み込んだ会話として、「トラックをどう活用して配送ルートを設計すれば、より効率的な物流が可能になるか」といった、具体的なオペレーションの検討にまで及びます。
こうした会話が交わされはじめる段階で、私たちが介入できると、当社のソリューションとお客様の課題が非常に強くフィットするということが、実際のインタビューを通して見えてきました。
つまり、“物流企画部門が本格的に動き出す瞬間”こそが、私たちにとって受注に向けて最短距離でアプローチできるタイミングである、という大きな学びを得ることができました。
こちらの図は、リレーションマップになります。実際に複数のお客様へヒアリングを行う中で、「お客様の人間関係や組織構造を一度可視化してみよう」と考え、作成したものになります。図中の名前などはマスキングしていますが、実際の組織にかなり近いかたちで描いています。
このマップを作成して強く感じたのは、大規模な企業であればあるほど、組織の中に多くの部門が存在し、それぞれの部門に多数のメンバーが所属しているため、“縦の関係”“横の関係”で摩擦が生まれやすいということです。
そのため、私たちが最初に「どの部門の誰と接点を持ったのか」、さらに「その会話の中でどんな人物が登場したのか」、そして「どの関係性において摩擦が生じる可能性があるのか」といった情報を丁寧に整理していくことがとても重要になります。
こうした情報整理を通じて、たとえば「どのタイミングで、どのような施策を打てば、私たちを応援してくれる社内のキーパーソンを後押しできるのか」や、「担当者がスムーズにプロジェクトを推進できる環境を、どう整えるか」といった具体的な戦略を描けるようになります。
このようなプロセスを経て、「社内のどの部門が本当の意味でのキーマンとなるのか」が明確になったことが、このリレーションマップから得られた大きな成果です。

夏:ここまで紹介したN=1インタビューを通じて顧客理解を深めていった内容をもとに、次に取り組んだのが、「その顧客像に対して、どんなマーケティング施策を打っていくか」の整理でした。
その中でも、最初に特に意識したのは、経営者視点での意思決定です。
マーケ施策の実施にあたり、やはり経営層にとって最も気になるのは、“お金の話”です。当時はまだマーケティング施策を本格的に展開した経験がなく、実績ベースでの予算化ができなかったため、私の進め方のスタイルでもあるのですが、「まずは必要最小限のコストで、特定の施策を小さく検証する」という方針でスタートしました。
そして、施策の検証を通じて、少しずつ「勝ちパターン」が見えてくるようになります。
「ここなら成果が出せそうだ」というポイントが明確になったタイミングで、そこにしっかりと投資をしていく。
このように、段階的にステップを踏みながら進めていくことで、最終的に大きな果実を得る、というのが、私にとっての“勝ちパターン”だと感じています。
この進め方については、社内の代表にも共有していました。
「ステップ1」の段階では、まず3ヶ月間の検証フェーズを設けて、試験的にいくつかの施策を実施し、そのなかで、うまくいったもの・うまくいかなかったものを整理し、検証結果として明確に洗い出したうえで、次の追加投資判断を行うという流れで当社代表に説明。投資リスクが小さいこともあり、即決でした。
そして、予算の方向性がある程度固まってくると、次に問われるのは「では具体的に何をやるのか?」という点になります。
ここで改めて感じたのは、私自身がこれまで長くBtoBマーケティングに携わってきた中で実感していることでもあるのですが、「ベタな施策は、やはりベタに効く」ということです。
特に今回は、施策実施期間が3ヶ月と比較的短かったため、次の二つの条件を満たす施策を優先して選定しました。
一つは「3ヶ月以内にクイックウィン(短期成果)が見えること」、もう一つは「継続して効果が出るかどうかを明確に判断できること」です。
こうした条件に沿って施策を選び、限られた予算ともしっかり紐づけながら、着実に実行に移していったのが当時の進め方です。
冒頭でも少し触れたかもしれませんが、当時、マーケティング部門は私ひとりだけでした。そのため、「すべてを自分でやるのは無理だ」と、正直すぐに諦めがついたんですね(笑)。
そこで、私が担う領域を明確に定めることにしました。具体的には、社内における戦略策定、社内調整、そして意思決定。この3つに全振りするという形で進めることを決めました。
では、オペレーションの部分をどうしたかというと、ここでKaizen Platformの皆さんに全面的に支援していただきました。社外のスペシャリストの方々を探すところから協力いただき、施策単位でチームを組成してもらいました。今回の検証フェーズでは、施策の実行部分をすべてお任せできたことで、最初から最後まで私は全体を俯瞰してディレクションする役割に集中することができました。
ここまでは「進め方」に関するお話でしたが、ここからは「実際にどんな施策を実行したのか」についてご紹介していきます。
とはいえ、最初からマーケティング施策に着手したわけではありません。まず取り組んだのは、セールス活動をスムーズに進めるための“仕掛け”づくりでした。
エンタープライズ攻略では、どうしてもリードタイムが長くなりがちです。そのため、マーケティングに入る前段として、「どう情報を共有するか」「どのように進捗を把握するか」といった体制を先に整える必要があると判断しました。
当社では、「JamRoll(AI議事録ツール)」と「Salesforce」を組み合わせて運用しています。たとえば、お客様との打ち合わせで「どんな会話があったのか」「今どんな課題を抱えているのか」といった情報を記録・共有し、定期的な会議体で「では、この案件をどう進めていくか?」をチームで相談しながら進める、という体制を構築しました。
この情報共有の仕組みがあったことで、検証フェーズでは非常に助けられました。
というのも、現場からの一次情報がなければ、マーケ側も「どこをどう改善すべきか」の判断精度がどうしても下がってしまいます。
ですので、「まず情報共有の仕組みを整える」というのは、個人的にも強くおすすめしたい準備プロセスだと感じています。
その上で、マーケティング部門としては、施策を1ヶ月単位で企画・実行するサイクルを回していきました。すべての施策を並行して実行しながら、それぞれの効果を検証し、必要に応じて改善していくという運用スタイルを取っていました。

その中で、最初から明確に決めていたことがひとつあります。「評価の基準」をどう設けるか、という点です。
私たちは各施策について「×」、「◯」、「◎」という3段階の評価項目を設定していました。そして、「◎」が取れるまで、施策をやり続けるという方針を、Kaizen Platformさんとも事前に合意し、徹底して実行しました。
では、「◎」の定義とは何か。それは、“業界水準を大きく上回る成果を出すこと”でした。
一度の施策で成果が出なくても、そこで終了とはせず、粘り強く改善を重ね、成果が出るまで何度もチャレンジを繰り返すスタンスで取り組んでいたんです。
検証の過程では負荷をおかけする場面も多々ありましたが、最終的には非常にハイレベルな成果指標が出る施策も生まれました。
この3ヶ月の中で強く感じたのは、エンタープライズのお客様と向き合ううえで、高品質なトークスクリプトやコンテンツを提供することが、いかに重要かということです。そこにしっかりとこだわり抜くことで、成果につながる。この実感こそが、今回の検証を通じて得られた最大の学びだったと考えています。
初期検証の3ヶ月間を経て、現在は次のステップとなる6ヶ月目のフェーズに入っています。ありがたいことに、私たちのロボット事業は非常に順調に成長しており、マーケティング部門がまだ存在していなかった当時と比べると、パイプラインの規模は5〜6倍にまで拡大しました。
現在は、そこからさらに推進力を高めていくフェーズにあり、新規事業の領域にも展開を進めている状況です。
冒頭でABMについて触れましたが、まさに今、ロボット事業で最初に顧客設定を行った企業の中から、別部門への展開や、より深いレイヤーの課題を新規事業の切り口として再設計しています。
そして、その中でクロスセルやアップセルの機会を創出し、1アカウントあたりのLTV(顧客生涯価値)を高めていく。これが、現在私たちが取り組んでいる新たなチャレンジです。
ーここからは、4つの質問を通じて、大事なポイントをより深堀りしていきます。
須藤:1つ目の質問です。エンタープライズ攻略の立ち上げで、まず何から取り組むべきでしょうか?
夏:僕自身、これまでに何度かマーケティング部門の立ち上げを経験してきたのですが、そのたびに強く感じるのは、「一次情報に触れることの重要性」です。
今回も、最初に取り組んだことのひとつが、N=1インタビューも兼ねて、自分自身で営業に行くことでした。営業資料も自分で作り、それを持ってお客様のもとへ伺い、直接お話をさせていただいたんです。
「こういう部分が気になるのか」「ここを解決してほしいと感じているのか」といったリアルな声を、実際にその場で聞かせていただけたことは、本当に大きな収穫でした。
正直に言うと、ある意味では“検証させていただいていた”ような部分もあったかもしれません。でも、そうして得られた情報は一切ブレがないんです。
だからこそ、その後に企画を立てる際も、「あの時のお客様に刺さった内容を基準にしよう」と考えることで、それに近い属性の方々にも自然と響いていく。そうした“再現性”を得ることができるのです。
まずはそこにチャレンジしてみる。それが、エンタープライズ攻略においても最短距離なのではないかと感じています。
須藤:野田さんたちも、エンタープライズ向けにサービスを提供されていますが、やはり同じような課題感を持たれているのではないかと思います。エンプラ攻略については、どのように取り組まれているのでしょうか?
野田:僕も最初はずっと一人でやっていたこともあって、やはりターゲットを決めることの重要性を強く感じていました。
僕たちの事業は業界特化型の“バーティカル”というより、“ホリゾンタル”な、かなり幅広い市場を対象にしています。だからこそ、業界や業種で区切るのではなく、「この業界の、この売上規模の、このレイヤーの、この職種の人」というように、解像度の高いペルソナ設計が必要だと考えています。
特に、僕たちがいる業界は競合プレイヤーも多く、差別化が非常に難しい領域です。たとえプロダクトに強みがあっても、それだけではなかなか選ばれないというのが現実です。
だからこそ、「ここを攻める」と明確に言い切れるくらいまで絞り込むこと。それを最初にやり切るのが、本当に大事だと感じています。

須藤:私たちKaizen Platformでもエンタープライズ攻略に取り組んでいますが、やはりターゲット設定は非常に重要だと感じています。
私たちの場合、自社のソリューションが合う業界が限られていて、「人材」「金融」「不動産」「BtoBサービス」など、顧客獲得単価が高い業界がスイートスポットになります。
その中で、「部長クラスにはこういう課題があるよね」といった形で掘り下げながら進めているのですが、夏さんの話にあった「倉庫を考え始めるタイミング」、つまり売上が伸びて倉庫の課題が顕在化する瞬間での接点が理想、というのはすごく納得感がありました。
でも実際、“絶妙なタイミング”って、狙ってアプローチできるものなんでしょうか?
夏:そのタイミングは正直今も悩み続けているところではあるんですけども……。
ひとつ補足させていただくと、先ほどの事業紹介では触れていませんでしたが、実は現在、コンサルティング事業のような取り組みも一部始めています。これを始めた理由がまさに、「どうやって最適なタイミングで接点を持つか」という課題に直結しているんです。
倉庫課題って、「さあ改善しよう」と明確に決まっている状態から始まるというより、たとえば「最近、現場が少し回りづらいかも」とか「業務全体を見直す必要がありそう」といった、曖昧で幅広い検討フェーズからスタートするケースが多いんですね。
そうした“ファジーな段階”に、コンサルという入口から関わることで、早い段階で課題を捉えることができる。そして、最終的に「やっぱり御社のプロダクトが必要ですね」と自然な形でつながっていく。
実際、コンサルをセットにしたことでタイミングをつかみやすくなった、という手応えはあります。
須藤:営業フェーズがまだ柔らかい状態だと、こちらとしても直接的な価値提供が難しい。でも、その段階から一緒に要件を検討する関係になれれば、そこに予算がつくし、提案依頼書(RFP)レベルの信頼関係にもなっていくんですよね。だからこそ、「コンサルをやったほうがいい」という話、本当にその通りだと思います。
野田さんたちも、「このタイミングで来てくれると理想的」というフェーズがあるかと思うんですが、逆に、「かなり後のフェーズで、方針をひっくり返す」みたいなこともあると思います。
その“フェーズの幅”に対して、どのような工夫をされているのかをぜひお聞きしたいです。
野田:僕たちのアプローチは基本的に「ISから入っていく形」なんですね。そして、ISが必要になるのは、やはりリードが発生したタイミングから。
だからこそ正直なところ、私たち自身では「より上流のフェーズ」に関するケーパビリティが、まだ十分とは言えないというのが現状です。
今まさに取り組んでいるのは、マーケティング施策の立ち上げ段階、「そもそも何をやるべきか?」という戦略フェーズから関わるという挑戦です。そこをご一緒できると、私たちの守備範囲が大きく広がるので、本当にありがたく感じています。
実際、いまもKaizen Platformさんと一緒に、そういった上流の設計から並走させていただいているところです。
リードが増えれば、ISの出番も広がり、やがてアップセルやクロスセルにもつながっていく。だからこそ、最上流から関われることは、私たちにとっても非常に意味のあるチャレンジになっていると感じています。
須藤:続きまして、2つ目の質問です。キーマンをどう見極めてアプローチした?について伺っていきます。
夏:本当に悩ましいテーマではあるんですけど、まず最初のステップは、先ほどご紹介したようなリレーションマップをつくることから始めます。とはいえ、最初からすべての関係者と会えるわけではないので、まずは「接点が持てた人」としっかり対話することが重要だと考えています。
たとえば、案件の進め方について率直に、 「このプロジェクト、こういうふうに進めたいのですが、どう思われますか?」と聞いてみると、本気で自動化を推進したいと考えている方であれば、具体的なアドバイスをいただけることが多いんです。
「◯◯さんを抑えてくれると助かる」「△△さんは僕の仲間だから巻き込んでほしい」といった、非常にリアルで生々しいコメントが返ってくるケースもあります。
そうしたやりとりの中で得た情報を、リレーションマップに反映していく。この作業を繰り返すことで、組織の構造を徐々に“上へ上へ”と登っていくイメージです。
このプロセスこそが、私たちの基本的なアプローチであり、いわば王道的なキーマン探索のやり方だと思っています。
須藤:なるほど。でもやっぱり、“キーマン”って、いろんなタイプがいますよね。
「決裁者ではないけれど、社内事情に詳しくて案内役になってくれる人」や、「偉い人の“ご意見番”として意見が重視される人」、「最終決定権は別の人が持っている」といったように、タイプは本当にさまざまです。だからこそ、誰がキーマンかを見極めるには、人間関係をスパイのように探っていく必要がある。
そしてそれは、ISとFSの連携が非常に重要だと思うんです。そのあたりの関係性の把握は、どのように進めていったのでしょうか?
夏:まさにおっしゃる通りで、「調整役」や「部門内で明確に影響力を持っている方」は非常に重要な存在です。
私たちの取り組みでは、そういったキーパーソン候補の情報を、関係者全員が把握できるように整理しています。
さらに、1件ずつアカウントプランを作成し、それをISに共有しています。会話の中でどんな質問を投げかけるべきか、具体的に想定しておくことで、IS側でも戦略的な視点を持って対話に臨むことができる体制を整えています。
須藤:野田さんたちはキーマンの見極めや社内力学の把握について、どう進めているんでしょうか?
野田:やっぱり外から見える情報と実際に会ってみてわかる情報って全然違うんですよね。
記事を読んだり、インタビューを見たりしても、正直なところ限界があります。
だからこそ、僕たちも“キーマンっぽい人”も含めて、まずは周辺の人たちに広くアプローチしていきます。その上で、実際にお話できた方には、営業っぽくならないように、「御社の中でどんなお仕事をされているんですか?」とか、「我々がお役に立てるとしたら、どんな場面ですか?」といった会話からスタートします。
そこから徐々に、組織の構造や人間関係を聞き出していくんです。これは、僕たちの中では全社的に徹底しているアプローチですね。
得られた情報はISにしっかりフィードバックして、そこから戦略的にアタックしていく流れを作っています。
あと、最近実際にあった話なんですが、ある企業で「部長が全部の権限を持っている」と思っていたら、実は課長がすべてを握っていた、なんてケースもありました。部長はただ頷いているだけ、という(笑)。
こういったことって、出社して一緒にランチをしたり、オフィスの空気を感じたりする中で初めてわかるんですよね。
もちろん、そうした観察も大切ですが、僕自身としては、「誰がキーマンかをじっくり見極める」というよりも、まずは会って、丁寧に話を聞き出すこと。それが一番いいアプローチなんじゃないかと感じています。
須藤:これはちょっと例え話なんですけど、僕がDXやAIの導入をお手伝いする時によく話すのが、“変革の三役”の話なんです。
江戸時代が終わるときって、まず徳川慶喜のような「危機感のあるリーダー」がいた。そして、勝海舟のように「現場を理解していて、人望もあって、組織を動かせる存在」がいた。さらに、坂本龍馬や西郷隆盛のように「外から動かす推進者」もいた。
この3タイプの登場人物が連携したからこそ、時代の転換がスムーズに進んだんだと思ってるんですよね。
だから、僕は企業の変革においても、「誰が“慶喜”なんだろう?」「誰が“勝海舟”で、“坂本龍馬”なのか?」っていうふうに見ることが多いんです。キーマンって言葉よりも、そういうふうに捉えると、「確かに、現場を動かせる人がいないと広がらないよね」って話にもなるんですよ。
逆に言うと、商談がうまく進まない時って、たいていこの“ピース”のどれかが足りていない。それを埋めにいかないといけない。
エンタープライズ営業って、営業トークがうまいとかそういうことじゃなくて、この“ミッシングピース”をどう埋めていくかが、すごく重要な仕事だと思ってるんです。でも、みんなつい「売ろう」としてしまうんですよね。「いやいや、違う。売る前に“埋めないと”、売れないんだよ」っていう(笑)。
これはなかなか外からは理解されづらい部分でもあって、だからこそ、この「キーマンの見極め」ってテーマ、ほんとにいい問いだなと思いながらお話を聞いてました。

須藤:3つ目の質問は「初期施策で工夫した点、そして失敗から得た学びは何か?」です。
さきほど夏さんのお話しで特に印象的だったのが、最初に実施した施策に対して「業界水準を大きく上回るスコアを出す」という目標を掲げたという点でした。非常にユニークだと思ったのですが、なぜそのような高い目標設定をされたのでしょうか?
夏:僕自身、これまでSMB向けのマーケティングと、エンタープライズ向けのマーケティングの両方を経験してきました。その中で特に強く感じているのが、エンタープライズの場合、「オーダーメイド感」が非常に求められるという点です。
これは製品に限った話ではなく、コミュニケーションのあり方にも同じことが言えます。たとえば、「私たちのために、ちゃんと考えてくれているんだな」と相手が感じられないと、なかなか次のステップには進めないんですね。
だからこそ、僕たちが最初に「ハイスコアを目指そう」と設定したのは、単なる目標数値ではなく、「その施策がどれだけ個別対応の精度を高められているか」を測るための評価軸だったんです。
実際、高いスコアが出ている施策というのは、しっかりと相手に合わせてカスタマイズされたコミュニケーションができているときに出ている。つまり、「業界水準を大きく上回るスコア」を目標に掲げたのは、成果というより“品質を測るための基準”として、最初からそこに据えていた、というのが背景になります。
須藤:もう少し深掘りしたいんですが、「オーダーメイド」って、よく使われる言葉ですよね。
でも僕は、課題って意外と似通っていると思っていて。たとえば、「この会社で起きているこの課題」、実は別の会社でもほぼ同じようなことが起きている、というケースって少なくないと思うんです。
だから見た目上はオーダーメイドっぽく見せていても、実際には“再現性のあるパターン”として設計されていることが多いんじゃないかなと。
そういう意味で、「セミオーダーに見えるようにする」って大事だと思うんですが、マーケティングとしては、やっぱり再現性がないとスケールしないですよね。そのあたりのバランスを、どのように考えていますか?
夏:まさにそこは、「効率」と「個別対応」のせめぎ合いになりますね。うちも完全なフルオーダーにはしていなくて、基本はセミオーダー型の設計にしています。
一定の「型」はあります。ただし、その中でもお客様が「これは自分のことだ」と感じられるポイントについては、必ずフルカスタマイズで対応しています。
たとえば、「課題設定の言い回し」「導入事例の選定」「コンテンツの導入部分」など、お客様の関心が高く、解像度が高い部分は、ピンポイントでしっかりとカスタマイズする。そうやって、効率と個別最適のバランスを取るようにしています。
須藤:野田さんたちは、この「再現性」と「オーダーメイド感」のバランス、どのように工夫されていますか?
野田:冒頭でオーダーメイドと話しましたが……すみません、うちも“フルオーダー”ではなかったです(笑)。全部を完全にパーソナライズしているわけではなくて、基本的にはセミオーダーでやっていますね。
なので、“見せ方”にはかなり気を配っています。結局、課題構造が似ていれば、勝ちパターンの内容は基本的に一緒なんですよね。狙っているペルソナがブレなければ、ニーズも大きく変わらないので、ある程度の“型”を持ちながら、微調整で対応しています。そのうえで、本当に相手ごとに合わせる“余白”の部分だけをしっかりカスタマイズする、というスタイルです。
あとは、僕が「自分ごと化」において特に重要だと思っているのが、“言葉を探すこと”なんです。その会社で使われている独特の用語や、誰かが強く推進している言い回しなど、言語が揃った瞬間って、ものすごく刺さるんですよね。
たとえば、「この課題をこう表現すると、その会社では“まさに自分たちの話だ”と感じてもらえる」みたいな言い回し。それを見つけるために、僕はお客様の資料をとにかく読み込みます。「このキーワードはよく出てくるな」とか、「これは誰かが社内で強く言ってるな」とか、そういった言葉の兆しを拾っていくんです。
地味ですが、一番刺さる表現につながる大事な作業だと思っています。
.jpg?width=1000&height=667&name=YSK_142%20(2).jpg)
須藤:最後、4つ目の質問です。マーケティングとIS、そして営業が連携するためのポイントはなんでしょうか。
夏:本当に悩ましいテーマですが、うちの取り組みとして効果的だったポイントをお話しします。
まず、マーケティングとISを、ひとつのグループとして運用しています。よく「ISはマーケティングに置くべきか、それとも営業に置くべきか?」という議論がありますが、うちでは明確にマーケティング側にISを配置しています。そして、一緒にコミュニケーションを設計する“箱”として機能させるようにしています。
では、営業とはどう連携しているのか?というと、 営業が使う商談資料をすべてマーケティング側で制作しています。
この運用には、大きく二つの狙いがあります。一つはマーケティングから営業まで、一連のコミュニケーションにおける「コンテンツの品質」を統一するため。もう一つはマーケティングが一次情報から離れてしまわないよう、現場のリアルな感覚を常に保つためです。
営業資料をマーケティングが作成することで、現場の状況に対する理解のズレを防ぎ、 ISを含めたチーム全体で、より精度の高い提案・営業活動ができるようになるという設計にしています。

須藤:野田さんたちのところでは、こうした連携まわりをどのように工夫されているのでしょうか?
野田:先ほど少しお話しした部分にも重なりますが、僕は「マーケティングとセールスをすべて同じ組織にしたい派」なんです。というのも、誰かがそこをきちんと見ていないと、マーケティング・IS・営業の連携って、どうしても深まりづらいんですよね。
たとえば、営業資料についても、うちではマーケティングが担当しています。実際にあったケースで、営業から「こういう資料が欲しい」と要望があっても、うまく意図が伝わらないことがありました。
ただ、そこを何度も細かくすり合わせていく中で、「マーケティングも徐々に理解してきたな」「営業も伝え方が変わってきたな」というお互いの歩み寄りが生まれてきたんです。
こういった連携が分断されたままだと、そもそも施策がうまく回らない。だからこそ、「誰かが全体を見て責任を持つ」という体制が、連携の前提として非常に大切だと考えています。
須藤:ありがとうございます。おっしゃる通り、組織の設計や責任の持たせ方ひとつで、コミュニケーションの質って大きく変わりますよね。
ー須藤さんからまとめをお願いします。
須藤:今回は「エンタープライズ攻略」というテーマで、ゲストのお二人とさまざまな話をしてきましたが、あらためて実感したのは、エンタープライズセールスはチームプレーであるということです。
僕の中では、アメフトやラグビーがすごく近いイメージですね。アメフトなら、投げる人、取る人、守る人、それぞれが役割を果たしてこそ1プレーが成立しますし、ラグビーも各ポジションが有機的に連携して動く。
エンタープライズセールスも同じで、個人プレーではなく、どう組織として連動し、“勝ちパターン”をつくっていくかが鍵になると、あらためて感じました。
そしてもうひとつ、強く感じたのが、「情報を制する者が勝つ」ということです。スパイ活動とまでは言いませんが(笑)、どれだけお客様のことを深く理解できているかが勝敗を分ける要素だと思っています。
夏さんも話されていたように、やはり「顧客理解」こそが最重要のファクターです。マーケティング、IS、FS、どの部署においても、顧客理解を徹底している組織は強い。今日のディスカッションを通して、その共通認識がよりクリアになった気がします。
私たちKaizen Platformとしても、引き続き皆さんと一緒にチャレンジを続けていけたらと思っています。
