
国内外のDX先進事例の紹介に加えて 今年話題となったAIの進化やDX人材育成までを網羅
#DX白書2023
大きな反響をいただいた「#DX白書2022」を大幅にアップデートし、ディズニー等のDXの次に進もうとしている企業の先進事例やそれらを取り巻くAI/Web3などのDXトレンド紹介、そしてDXを推進するための人材戦略まで、検討のヒントになる情報を多数詰め込んだ内容となっております。

国内外のDX先進事例の紹介に加えて 今年話題となったAIの進化やDX人材育成までを網羅
#DX白書2023
大きな反響をいただいた「#DX白書2022」を大幅にアップデートし、ディズニー等のDXの次に進もうとしている企業の先進事例やそれらを取り巻くAI/Web3などのDXトレンド紹介、そしてDXを推進するための人材戦略まで、検討のヒントになる情報を多数詰め込んだ内容となっております。

TikTokに興味はあるもののどうすればいいかわからない方
縦型動画を試してみたいけど、アサイン、ディレクションに対してノウハウが無い方
一度は試してみたけど、成果が出ず伸び 悩んでいる方
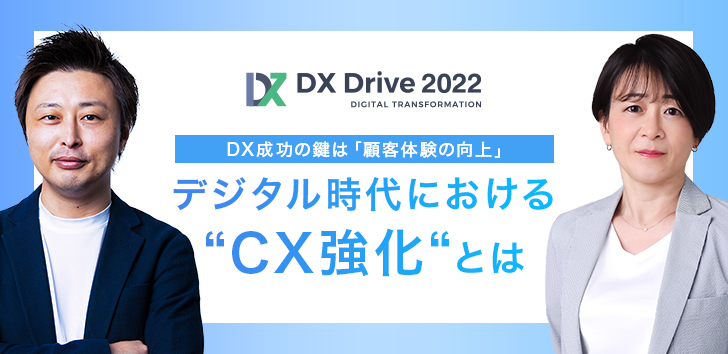
DX推進のご担当者、事業責任者の方
新規事業や組織改革を担う事業責任者の方
マーケティング担当、Web担当の方

著者: Kaizen 編集部

世界中で急速に進化する生成AI。そのスピードとインパクトは、単なる技術革新を超え、私たちの仕事や社会のあり方に大きな変化をもたらしています。本セッション「生成AIの衝撃〜話題のデータを見ながら、USの今を聞く〜」では、特別ゲストのシバタナオキ氏を迎え、Kaizen Platform代表の須藤憲司とともに、最新データをもとに生成AIの進化とアメリカ社会の現状、そしてその先にある未来の可能性について深掘りしました。
*本記事では、2025年6月3日(火)に開催されたイベント「KAIZEN AI ONEDER SUMMIT」の内容をお伝えします。
ゲスト
シバタ ナオキ
1981年生まれ。東京大学大学院工学系研究科技術経営戦略学専攻 博士課程修了(工学博士)。楽天執行役員、東京大学助教を経て、スタンフォード大学の客員研究員として渡米。米国シリコンバレーで起業。「決算が読めるようになるノート」(https://irnote.com/)を創業し、経営者やビジネスパーソン、技術者などに向けて決算分析の独自ノウハウを伝授している(2022年に事業譲渡)。著書は『MBAより簡単で英語より大切な決算を読む習慣』、『テクノロジーの地政学』(いずれも日経BP)。
須藤:まず『AI 2027』の話から始めようと思います。元OpenAIガバナンス研究者のDaniel Kokotajlo氏らが公開した超人的AIの影響についての予測シナリオで、「Race Ending(競争の結末)」と「Slowdown Ending(減速の結末)」という2つのエンディングがあります。

架空の会社がいくつも登場し、2025年前半には汎用型のAIエージェントがSlackやTeamsなどに入り込み、ルーチン業務の一部を引き受けるようになります。
その後、先進的な企業が有料版のAIを導入し始め、人員の再配置を検討するところから物語がスタートします。
2025年後半には、AIが「従業員」としての立ち位置を確立し、新人クラスのコーダーやリサーチャーが余りはじめます。労働組合は再訓練基金を要求し、アメリカ議会はAI労働者法案の準備に取り掛かります。ここからが面白く、2026年にはR&Dの自動化ブームが到来します。
今もAIのアップデートのスピードが速いのは、AI自身がAIを開発しているからだと言われていますよね?
シバタ: 間違いなくそうだと思います。それはもう否定できない事実として、少しずつ実現され始めていると感じますね。

須藤:2026年には、AIだけでなく、薬や素材といったフィジカルな領域も含めて、研究開発(R&D)の約半分をAIが実行するようになるという話が描かれていました。専門職も圧迫され始めるような光景です。
さらに、ハイテク企業では「人がAIを監査する」というモデルに移行するという展開もありました。
2027年前半になると、スーパーヒューマンコーダーのような存在が登場し、いわゆる20万体ものエージェントが数百万人分の労働力を提供し始める、という話になります。データセンターがオフィスを飲み込むような描写があり、中堅のエンジニア職が激減していくのです。
そして、各社がヒューマンレビューやAIガバナンス部門を新設します。
2027年後半には、社内の大半の人間が貢献不可能になるという衝撃的な一説もあり、結局、人間は企画や倫理判断だけを担うようになる、と描かれていました。
AIがあまりにも急速に発展しすぎるため、ユニバーサルベーシックインカム(UBI)の拡充を求める声が出る一方で、逆に成長を優先すべきだという意見もあり、政治が分裂していきます。
さらに、中国とアメリカの間でAI競争が激化し、GPUを準国有化すべきという議論まで巻き起こる、と。
最後のエンディングは2パターンに分かれていて、Race Endingの場合は失業が急増します。一方、Slowdown Endingの場合は5年間のモラトリアムを設けてAIの進歩を抑えようという流れになります。どちらの分岐でも、雇用の再設計やAI課税が国家レベルの議論の中心になるというストーリーでした。

シバタさん、これを読んでどのような印象を持たれましたか?
シバタ:まずアメリカでは、全体的にポジティブというか、「まあ、こういう感じになるよね」という意味で受け入れている人が多い印象です。
個人的には、良い意味でも悪い意味でも、アメリカと中国がこれだけAI開発で競争している状況では、核兵器のときと同じで、どちらかが手を緩めるという選択肢は現実的にはあまりないんじゃないかと思います。国家を守る以上、そこを緩めるというオプションは取りにくい。アメリカと中国が手を取り合って「(AI開発をこれまでよりも)ゆっくり進めましょう」となることは、おそらくほぼないでしょう。
そういう意味で、この小説に書かれていることが全て現実化するとは思いませんが、一部のことについては早い段階で現実になる可能性も十分あるのではないか、と感じています。
須藤: 実際に生成AIの雇用への影響という点で、シバタさんに面白いデータをお持ちいただいています。最新の生成AIモデルのIQデータです。

シバタ:IQを指標にするのは適切ではないという声もありますが、分かりやすいのであえて使いました。
最近登場した最新のモデル、特にOpenAI、Anthropic、Googleの3社から出ているものは、すでにIQが110を超えてきているんですよね。3ヶ月後ぐらいに登場する新しいモデルは、さらにIQが右側(高い側)に進んでいくのではないかと思います。
もはやIQというよりも、理論的に物事を考えたり、感情を扱ったりといった意味での知性の面でも、人間の平均を超え始めている印象があります。
私はすでに、自分の知性がAIに3〜6ヶ月ぐらいで追い越されるという前提で、自分の生活を設計するようにしています(笑)。
須藤:2025年にFRB(米連邦準備制度理事会)が発表した学部別失業率のデータも衝撃的でした。全75学部中、失業率トップ10にコンピューターエンジニアリング、コンピューターサイエンス、情報システムマネジメントといったコンピューター系の学部が入ってきたんです。
前年度と比較すると、コンピューターエンジニア系は約3倍に急上昇していて、情報システムマネジメントも同じように大きく上がっています。

シバタ:シリコンバレーもソフトウェアエンジニアがものすごく多い場所なので、失業率の高さを体感しています。スタートアップからGoogleのような大企業までソースコードをAIに任せているので、エンジニアという職種は、確実にこれまで程はいらなくなるだろうなと思いますね。
特にソースコードを書く仕事は、LLM(大規模言語モデル)が扱いやすいタイプの仕事の一つで、数学的に解決できるということと、学習データが世の中に大量にあるので、AIに置き換わりやすい職種だと思います。
今まで最も卒業生の給料が高かった学部が、急に人がいらなくなるというのは、まさにこの生成AIの革命を象徴していると感じますね。
須藤:GAFAM(Google、Apple、Facebook、Amazon、Microsoft)の売上は伸びているのに従業員数が増えていないどころか減り始めている、というデータがあります。これはテック業界全体でも同じ傾向で、従業員数が売上の伸びと連動しなくなったというのが、衝撃的でした。

これはアメリカではどのように受け止められているんですか?
シバタ:やっぱりエンジニアの採用が明らかにスローダウンしていますし、会社によってはレイオフしているところもあるので、そういう意味では周知の事実という感じになっていますね。
一方で、従業員数自体は減っていないんですが、設備投資、特にGPUやデータセンターへの投資がものすごい勢いで増えていますよね。
おそらくこのグラフに載っている会社すべて、フリーキャッシュフローで見ると、前年よりかなり利益が落ちている状態なんじゃないかなと思います。
人に投資するのではなく、GPUやデータセンターに投資しているのが、今のいわゆるGAFAMの特徴だと思います。

須藤:実際、直近のMicrosoftのレイオフは衝撃的でしたね。ソフトウェアエンジニアの人員削減が本格的に始まったということで話題になりました。
「私の夫がアルゴリズムでMicrosoftをクビになった」という投稿がものすごくバズっていましたが、AIレイオフのニュースはアメリカではどのように報道されているのでしょうか?
シバタ:こうした話題は頻繁に出てくるので、私なんかはもう見慣れてしまった感があります。
業務経験豊富なシニアな人は残ると思うんですが、特に比較的経験の浅い人たちは、「AIにできないことで何ができるんだ?」というのをジョブディスクリプション(職務記述書)やインタビュー(面接)で問われるので、かなり厳しい状況なんじゃないかなというのが正直なところです。
須藤:日本ではまだ人手不足が深刻で、新卒採用もかなり進んでいるので、アメリカとのギャップを感じますね。こういうニュースはとても興味深いです。
どの会社のリリースにも「人を削ってGPUに投資します」と書かれていて、なかなか衝撃的だなと思って見ていました。
国内ではリクルートが1万6000人中4000人くらい削減するという話がありましたが、実際にはそれでも全く問題なく回っていますというリリースが出ていました。

この動きについて、アメリカ社会ではどのように受け止められているのでしょうか?
シバタ:当然、これをすごく嫌だと感じる人もたくさんいて、多分数でいうとそういう人の方が多いんじゃないかと思います。
ただ、私のように最先端のAIの会社を毎日のように見ている人間からすると、その感覚が麻痺してしまい「まあ当然こうなるよね」と客観的に見てしまう自分がいます。
良いか悪いかは別として、間違いなくこういう流れになると思います。過去の産業革命を振り返っても、当時は人口の9割が農業をやっていたのが、産業革命後には10%以下になりました。短期間でそのように変化したので、ジョブディスクリプションが明確なアメリカのような国では、こうしたレイオフはこれからも非常に多くなると思います。
逆に日本のように、その人の特性に合わせて雇用する仕組みがあまりない場合は、あまりレイオフという形で表には出てこないかもしれません。けれど、今までやっていた仕事と今後5年、10年先の仕事が大きく変わっていくという点では、ほとんど同じなんじゃないかなと思います。
須藤:Googleが反トラスト訴訟で提示したデータが面白かったので紹介させてください。

このデータは、ChatGPTのデイリークエリ数が12億回を超えてることを示しています。要は、Googleが「GeminiよりもChatGPTのほうがすごいんだぞ」っていうのを、ちょっと皮肉っぽく示しているようなデータです(笑)。
また、トラフィックシェアの2025年3月から4月の1ヶ月の変化に関するデータも衝撃的でした。

ChatGPTが世界で5番目にトラフィックの多いサイトになっているんですよね。しかもInstagramを超えようとしていて、わずか1ヶ月間で13%も増加しているんです。しかも、他のサービスは全部減っています。
シバタ:私も今まで検索していたことは確実にAIに聞くようになりましたね。家族と話す時間よりもAIと話す時間のほうが長い日もあるんじゃないかというくらいです(笑)。
須藤:残念ながら、僕も同じです(笑)。もう検索という概念自体がなくなってきていて、本当にAIに聞くようになったなと感じます。ChatGPTのメモリ機能の進化も凄まじいですよね。
シバタ:メモリ機能、つまり過去の会話を記憶するというのは、人間にとっては当然のことですが、AIが実現してくれるようになって、人間っぽくなったなと思いました。
個人的に衝撃的だったのは、今年に入ってからAIがウェブサイトの情報を自動で検索して、その内容をまとめてくれるようになったことですね。
今まではDeep Searchとかを使わないとできなかったことが、普通にできるようになってきた。自分の脳がパーソナライズされた記憶を覚えていてくれて、インターネット上の情報を簡単に探してきてくれる。
しかもAIって、1秒間に100ページとか読めるじゃないですか。僕なんか絶対無理ですよ(笑)。だから、自分の脳がすごく拡張されたような感覚が強くなりました。
須藤:世界全体の検索数シェアのグラフをみてみると、ChatGPTがランクインしつつあるんですよね。しかも前年比で3倍のスピードで伸びているという衝撃的なデータも出ているようです。

検索業界からするとかなり怖いだろうなと思ったんですが、Googleの方々はどんなふうに感じているんでしょうか?最近「AIモード」が登場しましたよね。
シバタ:Googleからすると、間違いなく脅威だと思います。ただ、Google上に出てくるAIサマリーは、まだ性能的にChatGPTには劣る部分があって、Googleとしては「イノベーターのジレンマ」をどう超えるかが非常に難しいところだと思います。
「AIモード」は実際に試しましたが、シンプルな検索ならAIがまとめてくれるのですが、複雑な問いになるとChatGPT o1などのReasoningモデルのほうが圧倒的に優れている印象です。
須藤:今、検索上位はほぼ広告の売上に支えられていて、Meta、Amazon、ByteDance、Apple、Googleといったプラットフォームを合わせると、ものすごく大きな市場になっていますよね。この広告モデルって、AIの登場でどう変わっていくんでしょうか?
シバタ:ChatGPTは間違いなく広告プロダクトを出してくると思います。
FacebookやInstagramは検索連動広告ではないのであまり打撃を受けないかもしれませんが、GoogleやAmazonのような検索広告領域には大きな影響が出るでしょうね。特にショッピングサーチ領域への影響は大きいでしょうし、中国ではTikTokやAlibabaも同じような試みをしてくる可能性があると思います。

須藤:UX市場についても見てみましょう。現在の市場規模は31.28兆円となっています。今後10年、生成AIの登場でUX市場はどのように変化していくと思いますか?

シバタ:まず、「AIとハサミは使いよう」だと思っていて、必ずしもマイナス面ばかりではありません。
特に、この31.28兆円市場の中でも物流・フルフィルメント領域、約2.5兆円の部分では、AIを投入して「コスト削減」を目指すのではなく、「顧客体験の劇的向上」を目指して使う企業が増えています。
例えば、配送日数を3日から1.5日に短縮するといった形で、体験改善にAIを活用している企業のほうが成功している印象です。
「同じ予算・同じ人数で2〜3倍の価値を提供する」という視点でAIを使う企業が、結果的にうまくいっているな、というのが実感です。
須藤:AIは「人の仕事を奪うもの」と見られがちですが、AIをどう使えばいいのか最後にメッセージをお願いします。
シバタ:コスト削減ばかりを目指すと、UXや体験の質が向上しないままで終わってしまい、結果的に失敗してしまうことが多いです。
まずは、「人間にはできないけれど、とても便利な体験」をAIで作って、その結果として生まれる「圧倒的な仕事量(生産性)の増加」を作り出す流れが成功しやすいと思います。
AIは「人間に代わる存在」ではなく、「人間を拡張し、UXを飛躍的に向上させるための道具」として使うのが一番いい形だと思います。