
国内外のDX先進事例の紹介に加えて 今年話題となったAIの進化やDX人材育成までを網羅
#DX白書2023
大きな反響をいただいた「#DX白書2022」を大幅にアップデートし、ディズニー等のDXの次に進もうとしている企業の先進事例やそれらを取り巻くAI/Web3などのDXトレンド紹介、そしてDXを推進するための人材戦略まで、検討のヒントになる情報を多数詰め込んだ内容となっております。

国内外のDX先進事例の紹介に加えて 今年話題となったAIの進化やDX人材育成までを網羅
#DX白書2023
大きな反響をいただいた「#DX白書2022」を大幅にアップデートし、ディズニー等のDXの次に進もうとしている企業の先進事例やそれらを取り巻くAI/Web3などのDXトレンド紹介、そしてDXを推進するための人材戦略まで、検討のヒントになる情報を多数詰め込んだ内容となっております。

TikTokに興味はあるもののどうすればいいかわからない方
縦型動画を試してみたいけど、アサイン、ディレクションに対してノウハウが無い方
一度は試してみたけど、成果が出ず伸び 悩んでいる方
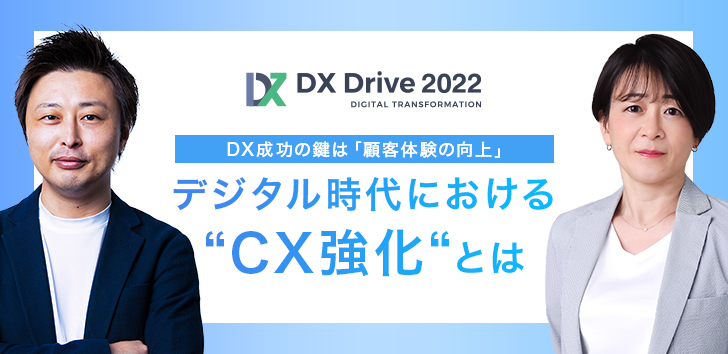
DX推進のご担当者、事業責任者の方
新規事業や組織改革を担う事業責任者の方
マーケティング担当、Web担当の方

著者: Kaizen 編集部

日本企業が直面する深刻な人手不足。その裏で、顧客体験や業務の質が低下している現実があります。Kaizen Platformでは、この状況を打破すべく「Magical UX」というAI戦略を打ち出し、「人間では実現できない、魔法のように便利な体験」を提供することを目指しています。本セッション「Kaizen PlatformのAI戦略〜Magical UXのご紹介」では、Kaizen Platform代表の須藤憲司がその取り組みをご紹介しました。
*本記事では、2025年6月3日(火)に開催されたイベント「KAIZEN AI ONEDER SUMMIT」の内容をお伝えします。
今の日本国内を見渡すと、どの企業も深刻な人手不足に直面しています。そのため、顧客体験の質が低下している状況です。たとえば、コールセンターでは待ち時間が長くなり、免許更新も「マイナ免許証」の手続きが2か月待ちと言われて諦めざるを得ないこともあります。
こうしたオペレーションのボトルネックがUXの損失を生み出していますが、一方で、生成AIの活用はまだ限定的です。

私はまず、社内で生成AIを積極的に活用しようと考え、ChatGPTを会社で契約し、全社員に使ってもらうところから始めました。ところが、実際には利用率が8〜10%程度だったのです。そこから「どうすればAIをもっと活用してもらえるか」という試行錯誤が始まりました。

その過程でわかったのは、多くの人が「どう質問すればいいのかわからない」「プロンプトを打っても結果がしっくりこない」「どう修正したらいいのかわからない」など、ハードルが高いと感じているということでした。加えて、生成AIには得意・不得意があり、どのツールを使えばいいのかの選択も簡単ではありませんでした。
そこでまずSlackに議事録を生成するAIエージェントを導入しました。
たとえば、会議の録画URLをSlackに投稿するだけで、その会議の議事録が自動で生成されます。会議に参加していない人でも「○○部長の発言は?」と質問すれば、録画をもとにAIが回答してくれます。さらに「ネクストアクションは?」と聞くと、AIが次の行動を提案してくれるのです。これが社内で爆発的に活用され、AIの利用が一気に広がりました。
この経験から学んだのは、「普段使ってるサービスを自然に使っていたらAIが使われていたという体験じゃないと生成AI活用は進まない」ということ。「どこで生成AIを使えるようにするか?」が極めて重要なのだと気づきました。実際、他社でも「自社でGPTを作ったが利用が進まない」という話をよく聞きます。Teamsなどの普段使うツール内でAIが使えるだけでも状況は変わります。私たちも、Slackだけでなく、さまざまなツールから呼び出せるAIエージェントの開発を進めています。

私たちはAI活用を3つのステップで進めています。フェーズ1は「今の業務の中でAIを試す」、これはある程度進んできました。フェーズ2は「AIが主役で人がサポートする」。現在はこの領域に取り組んでいます。そしてフェーズ3は「完全自動化」。AIが営業から請求業務まで一気通貫で対応する世界です。一気には進まないため、フェーズ2を着実に進めています。


ただし、AIのアウトプットをそのまま使わないと学習が進みません。たとえば、動画制作をする際に「ブリーフィング」と呼ばれる資料を作成します。これは、プロジェクトの目的、ターゲット、メッセージ、コンセプトなど、制作に必要な情報を簡潔にまとめたものです。
このブリーフィング制作に生成AIを導入したところ、制作時間は2時間から1分に短縮。初稿納品が2週間から2日に縮まり、一人あたりの生産性が10〜20倍という結果になりました。
しかし、当初はPDCAサイクルがうまく回りませんでした。その原因は、ディレクターがAIがアウトプットしたものをそのまま使用せず、修正を加えてしまったからです。そうすると、AIによるオペレーションが徹底されず、導入効果が見込めません。
なぜAIに全て任せず、手を加えてしまうのか。これは「ゼロリスク主義」や「AIに仕事を奪われるかもしれない」という本能的な恐怖感があるからです。これを乗り越えないとAI活用は進まないと感じました。
AI活用は、最初から「コスト削減」を目的にするのではなく、「人間にはできない便利な体験」を作ることから始めるべきだと考えています。結果として人の仕事が増え、そこから業務効率化に進むのが賢いやり方です。

このような経緯を踏まえ、私たちは「普段使っているサービスを自然に使っていたら、AIで便利になっていた」というUXをつくることにしました。
ただ、システムの制約でUXが変えられないなど既存のサービスに生成AIを組み込むのは簡単ではありません。

そこで、私たちが以前から提供している「タグを入れるだけでUXが変えられるA/Bテストツール」から生成AIを呼び出せるようにし、さまざまな既存システムでAIを活用できる仕組みを整えました。これが「Magical UX」です。

Magical UXでは、「ユーザー体験をサポートする2つのエージェント」と「従業員の業務をサポートするAI-Coworker」を提供しています。今回は「ユーザー体験をサポートする2つのエージェント」について重点的にお話ししたいと思います。
多くのユーザーは、まず情報を探したり比較したりし、最終的にはすぐに予約・資料請求・ダウンロード・購入といった「コンバージョン」に進みたいと考えています。欲しい情報が自然に届き、申込みが一瞬で終わる“魔法のような体験”を実現するために、私たちは「Kaizen Personalize Agent」と「Kaizen Conversion Agent」の2つのエージェントを開発しました。

「Kaizen Personalize Agent」は、ユーザーがウェブサイト上で検索した条件(例えば、場所・価格・面積など)をAIが覚えておき、離脱後もLINEなどで最新情報をお届けできる仕組みです。
例えば、
これにより、ウェブとLINEをシームレスにつなぎ、ユーザーの検索行動を追跡しながら「寄り添う体験」を提供します。
さらに、条件の更新や在庫の変動にも対応し、在庫切れの際には「在庫が入りましたよ」といったリアルタイム通知も実現できます。これを人手で行うのは大変ですが、AIが自動で対応してくれるので機会損失を防げます。

続いて、「Kaizen Conversion Agent」についてです。ユーザーがフォームで個人情報(名前、住所、電話番号など)を入力する際、入力作業が煩雑で離脱率が非常に高いという課題があります。実際、最後のフォーム画面で6〜7割が離脱すると言われています。
そこで「もうユーザーに入力させない」という発想から、AIが代わりにフォーム入力を行う仕組みを作りました。
例えば、
これにより、フォーム入力の手間が大幅に削減され、最大で90%の時短効果が確認されています。実験では、従来のフォーム改善で10〜20%程度の改善率だったものが、この自動入力機能で30〜50%のコンバージョン改善が可能になりました。
これらのAIエージェントは成果報酬モデルを採用しており、導入時の開発費用はいただかず、実際に成果が出た分だけ料金をいただく形にしています。
また、AIエージェントの成果が他の施策と重複してカウントされることを防ぐために、あらかじめ10〜20%程度の対象外のトラフィックを設け、そこと比較して計測することで純増分のみを正確に成果として評価できます。

これまで、AIエージェント導入において最も大きな壁となったのが「社内説明」でした。「実績があるのか」「どのくらい効果が出るのか」など、使ったことがないからこそ説明が難しく、導入が進まないことが多かったのです。私たちは、こうしたリスクを一緒に背負いながら、お客様とリターンを分かち合うビジネスモデルで普及を後押ししていきたいと考えています。
最終的には、ドラえもんのひみつ道具のように、誰でも簡単に未来の技術が使える世界を目指しています。その実現のために、私たちは今後もAIエージェントを進化させ、皆様のビジネスや暮らしをより便利に、ハッピーにしていきたいと思っています。