
国内外のDX先進事例の紹介に加えて 今年話題となったAIの進化やDX人材育成までを網羅
#DX白書2023
大きな反響をいただいた「#DX白書2022」を大幅にアップデートし、ディズニー等のDXの次に進もうとしている企業の先進事例やそれらを取り巻くAI/Web3などのDXトレンド紹介、そしてDXを推進するための人材戦略まで、検討のヒントになる情報を多数詰め込んだ内容となっております。

国内外のDX先進事例の紹介に加えて 今年話題となったAIの進化やDX人材育成までを網羅
#DX白書2023
大きな反響をいただいた「#DX白書2022」を大幅にアップデートし、ディズニー等のDXの次に進もうとしている企業の先進事例やそれらを取り巻くAI/Web3などのDXトレンド紹介、そしてDXを推進するための人材戦略まで、検討のヒントになる情報を多数詰め込んだ内容となっております。

TikTokに興味はあるもののどうすればいいかわからない方
縦型動画を試してみたいけど、アサイン、ディレクションに対してノウハウが無い方
一度は試してみたけど、成果が出ず伸び 悩んでいる方
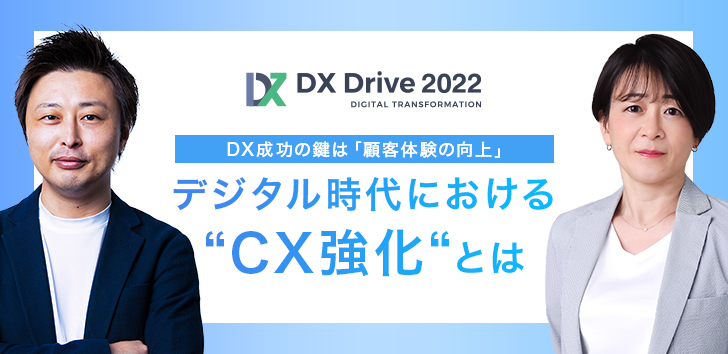
DX推進のご担当者、事業責任者の方
新規事業や組織改革を担う事業責任者の方
マーケティング担当、Web担当の方

著者: Kaizen 編集部

日本企業がAI活用に取り組む中、特にバックオフィス業務では課題が山積しています。そんな中、Kaizen Platformはマネーフォワードと共同で「AIエージェント」の開発に挑戦。ユーザー視点を取り入れたUX改善、システムの連携、そして運用面まで、現場で感じたリアルな課題とその解決策が詰まった事例をお届けします。本セッション「バックオフィス向けAIエージェントの共同開発」では、マネーフォワードビジネスカンパニーCPOの廣原亜樹氏をゲストにお招きし、Kaizen Platform代表の須藤憲司、AI STUDIO チームの河部裕と共にプロジェクトの裏側や実践から得た学びを語りました。
*本記事では、2025年6月3日(火)に開催されたイベント「KAIZEN AI ONEDER SUMMIT」の内容をお伝えします。
ゲスト
株式会社マネーフォワード
執行役員
マネーフォワードビジネスカンパニーCPO
廣原 亜樹
須藤:まずはマネーフォワードさんの概要を廣原さんよりご説明いただきます。
廣原:当社は創業から13年のプライム上場企業で、IT企業としてグループ全体で約2600名の従業員が在籍しています。
皆さんの中には、家計簿アプリ「マネーフォワード ME」で当社をご存じの方もいらっしゃるかもしれませんが、その裏側では銀行・証券・クレジットカードなどのデータを自動で収集・取得する「アカウントアグリゲーション」という技術を活用しています。この技術を基盤に、家計簿アプリだけでなく、会計帳簿の自動作成や経費精算の自動化、金融機関向けの各種サービスも展開しています。

直近では「AI Vision 2025」という形で当社のAI戦略を発表しました。ここでポイントを簡単にご説明します。
大きく3つの柱があります。
1つ目は、当社クラウド製品へのAIエージェント機能の実装です。
2つ目は、当社だけでなく他社にもプラットフォーム上でエージェントを一緒に作っていただき、ユーザーに多様な価値を提供するというプラットフォーム構想です。
3つ目は、プロダクト単体ではなく、AXコンサルティングをセットにして価値を提供していく取り組みで、昨年末にスタートしたマネーフォワードグループ内のコンサルティング会社で対応していきます。
河部:マネーフォワードさんとは、「マネーフォワード クラウド経費」の経費登録機能について、POC(概念実証)を一緒に進めています。
具体的には、Slack上でレシートをアップロードすると、そのまま経費登録まで自動で進められる仕組みを目指しています。

須藤:実際、私も毎月経理担当から「経費申請がまだ出ていません」と催促されることが多くて、こういった手間を減らしたいです(笑)。
河部:例えば、交際費などの扱いでは、金額や利用シーンによって仕訳や税率が変わるため、ユーザーがどれを選べばいいのか迷ってしまうことが多いんです。そこをAIがサポートし、「この条件ならこれに当てはまります」と提案してくれるようにしたいと考えています。

須藤:すでにモックも動いているんですよね?
河部:はい。裏側はまだ完全ではありませんが、Slack上でレシートをアップロードし、OCR解析後に経費登録ボタンを押すと、マネーフォワード クラウド経費に登録できるデモを作っています。
須藤:今回このプロジェクトをKaizen Platformと進めようと思った理由をお聞かせください。
廣原:理由は大きく2つあります。1つ目は、Kaizen Platformさんがマネーフォワード クラウド経費のユーザーであることです。
須藤:そうなんです、私自身が経費精算に困っているから、なんとかしてほしいなと(笑)。
廣原:ユーザーさんの知見を入れるっていうのは非常に重要なので、そこが1つポイントでしたね。
2つ目は、Kaizen Platformさんがエンタープライズ向けのUXに強みを持っており、UX観点での専門性を補完していただけるのではないかと考えたからです。

須藤:実際にプロジェクトが始まってみて、どのような印象をお持ちですか?
廣原:毎日とても楽しくプロジェクトを進めさせていただいていますね。
かなり具体的なお話になるのですが、私たちは今、AIエージェントのプラットフォームを開発しており、その実装を進めているところです。
プラットフォームの開発において、エージェントを開発する側の視点がとても重要ですが、特に外部からエージェント開発に参加される場合、プラットフォーム側に必要な機能が備わっていないと作業が進めにくかったり、プラットフォームのポリシーがしっかり定まっていないと良いものが作りにくいという課題があると実感しています。今まさに、そのあたりを多く学ばせていただきながらプラットフォーム開発を進めています。
この取り組みを通じて、私たちのプラットフォーム自体も大きく改善されるきっかけになっていますし、エージェントそのものも、より良い形でユーザーに届けられるようになると感じています。
須藤:河部さんは、プロジェクトを進める中で気づいたことはありますか?
河部:今、廣原さんがおっしゃったことにも繋がるのですが、チャットのUXについては、WebでもSlackでも、最近はかなりKaizen Platformの中で検証しています。なので、そこはしっかりお手伝いできるところだと思っています。
また、先ほども少し触れましたが、今回は経費登録の部分だけをPoCとして取り組んでいますが、結局、ユーザーさんの立場から見ると、会計でも経費でも、最初は「チャットでAIに話しかける」というところからスタートするわけです。
だからこそ、体験に一貫性がないと違和感が出てしまうと感じています。経費登録だけでなく、AIエージェント全体として「AIに話しかけてスタートする」という共通体験が必要だと思いますし、どのプロダクトを使っていても同じような体験になるようにしないと、ガラパゴス化してしまうなと学びました。
須藤:マネーフォワードさんではプロダクトごとに開発者が異なりますよね。そうなると、個別に見れば「これはいいな」と思えることも、全体で見ると「こうじゃないよね」ということが起こりやすいのではないかと思うんですが、そのあたりはやはり悩ましいところなのでしょうか?
廣原:おっしゃる通りで、とても悩ましいですね。弊社は各モジュールやプロダクトの専門性が非常に高いので、全体を網羅的に理解しながら開発を進められる人材を揃えるのは、正直ほぼ不可能に近いレベルです。どうしても縦割りになりがちで、そこをいかにユーザー体験として横の統一感と分かりやすさを提供できるかというのは、本当に難しいところです。
今回のエージェント開発においても、まさにチャレンジングなポイントだと感じています。

須藤:複数の事業やプロダクト、サービスを持っている会社さんが多いと思いますが、その中でAIエージェントを導入するとなったとき、単一のサービスだけをカバーするエージェントだと正直性能が低いですよね。もっと全体をカバーしてほしいのが本音だと思います。でも、実際のところ社内は分業されているので「これはこう」「あれはこう」となってしまうのが現実ですよね。
廣原:しかも、部署によって優先順位が違う場合もあります。今回ご一緒している「経費」の領域は、APIも揃っていて比較的やりやすかったのですが、他のプロダクトやプロジェクトは進み具合もそれぞれ違いますからね。
ただ、今回のエージェント構想の本質的なゴールとしては、「業務ごとにそれぞれのUIを開いたりすることなく、エージェントとの対話だけであらゆる業務を行える」という世界観を目指しています。これを実現するには、結局のところ、各プロダクトの裏側に、高度な業務ロジックと業務データをいかに網羅的に持っているかが重要になります。
須藤: 確かに、バックエンドのロジックとデータがすべてですもんね。もしこの部分がチープだと、どれだけ上にエージェントを被せてもきちんと動かない。その意味では、SaaSの品質向上がやはり原点なんですね。
廣原:おっしゃる通りです。そこは私たちとしても追求し続けています。そのうえで、どうやって上にエージェントをヘッドレス化させたSaaSに被せていけるかが、今回のプロジェクトのポイントだと思っています。
須藤:河部さん、今回のプロジェクトは経費精算から始めていますが、マネーフォワードさんでは人事などいろいろなサービスも展開されていますよね。こうした複数のプロダクトを横断するエージェントを作るうえで感じている難しさはありますか?
河部:複数のサービス、例えば経費の登録や勤怠管理などを紐付けて連携させることは想定されると思います。ただ、そのときにAIとしてユーザーと会話するエージェントは、当然両方の知識を持っていなければいけないですよね。経費にも詳しく、勤怠にも詳しく。
これが3つ、4つと増えていくと、果たしてAIエージェントがそれをすべて覚えていられるのか、という問題が出てきます。
例えば「経費担当のエージェント」「勤怠担当のエージェント」といった分担をして、それを汎用エージェントが統括する形がいいのか。あるいは、一つのエージェントが全部覚えるのか。そのあたりの組み合わせ方は、今まさに試行錯誤しているところですし、ここが大きなチャレンジだと感じています。

須藤:マルチエージェントの話に関連して、例えば経費精算と人事など、少しドメインが離れている場合ってありますよね。そういうときは、エージェントを分けて汎用的なエージェントを呼び出す形の方がいいのか、現時点ではどんな進め方が良いとお考えですか?
廣原:基本的に、ものすごく複雑なことをしない限り、マルチエージェントの作り方にはいくつかパターンがあります。
その一つが「スーパーバイザー形式」と呼ばれるものです。これは親エージェントがいて、各子エージェントに「これはこうしてください」「あれはこうしてください」とタスクを振り分ける仕組みです。業務タスク系にはこの形が性能的にも良いとされています。
逆に、エージェント同士が勝手に会話して協調するタイプもあるにはありますが、業務ユースケースにはあまり向かないと感じています。
須藤:つまり、指示命令系統がしっかりしていて、親エージェントが子エージェントに「これやって」と振っていく方が業務には合っているんですね。
廣原:こういったバックオフィス系の業務には、そういう形の方が合っていると思います。
私たちが今回取り組んでいるエージェントも、実はかなり広いスコープを想定していますが、登り方は堅実に、実際にできるところから進めていく必要があると考えています。

須藤:今後のスケジュール感としては、どんなイメージをお持ちですか?
廣原:マルチエージェントの話にもありましたが、あまりにもスーパーなエージェントをいきなり作ろうとすると、どうしても現実離れしてしまいます。
特にエンタープライズのお客様の場合、人事の中でも担当が分かれていたり、経理の中でも担当が分かれていたり、仕事がきっちり分担されていますよね。ですので、同じようにエージェントも分担して作っていきたいと思っています。
私たちは「デジタルワーカー」と呼んでいますが、例えば「このエージェントは経費の異常値だけをチェックする」といった具合に、一つひとつタスクを持つエージェントを人間の仕事の分担と同じような単位で揃えていく予定です。そして、それらをまとめて指示する役割の親エージェントを作るという形で進めたいと考えています。
まずは一つずつシングルタスクのエージェントを作っていき、年内にいくつかリリースする計画です。
須藤:ありがとうございます。我々も同じで、「従業員の業務をサポートするAI-Coworker」として、まずはシングルタスクのものから作っています。例えば、ログを作る人、タスクを分解する人、プレスリリースを作る人などですね。
シングルタスクだと性能がとても良いので、例えば「プレスリリースを書きたい」と言えば、そのエージェントがきれいに仕上げてくれる。そんなエージェントをいくつか作って、少しずつブラッシュアップしていくのが現実的かなと思っています。
須藤:私たちと一緒にプロジェクトを進めていく上で、今後期待していることをぜひお聞かせください。
廣原:まずは一つ目として、特にエンタープライズのお客様向けに、しっかり便利に使っていただけるように仕上げていきたいと思っています。
当社はバックオフィス機能も豊富に持っていますので、経費精算だけにとどまらず、同じシリーズとして揃っていて、その中でUXが統一されていると非常にいいなと感じています。
そういった意味でも、継続的にエージェントを作っていけると良いなと思っています。
須藤:ありがとうございます。私たちも今回、経費精算からスタートしていますが、最終的にはバックオフィスの業務全体を楽にし、従業員の皆さんが働きやすくなることを目指しています。
これからも、こういった取り組みを進めていくつもりですので、ぜひ一緒にプロジェクトを進められたら嬉しいです。