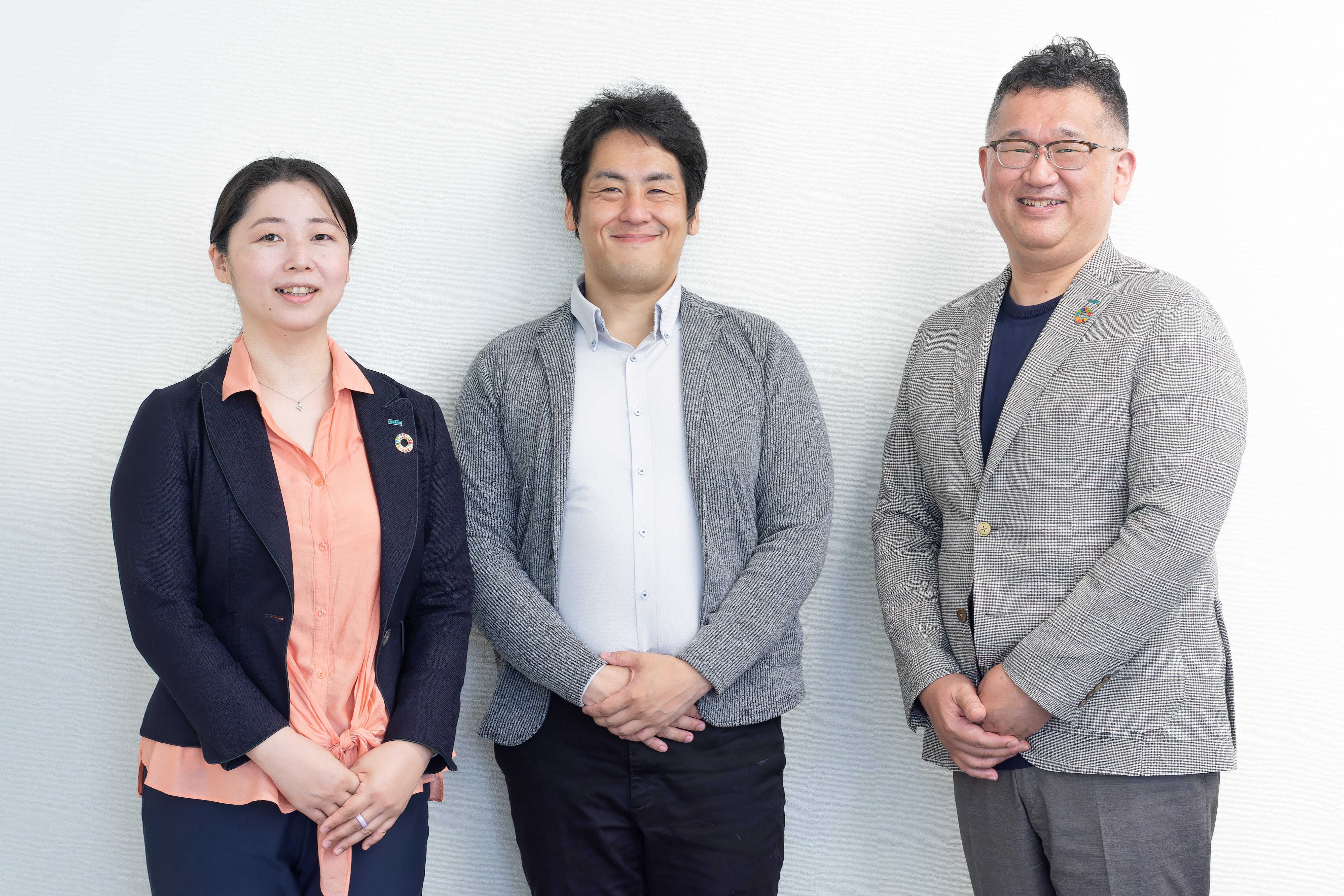ECの普及に伴い、物流のニーズが高まる一方で、人口減少などによる人手不足が社会問題にまでなっている物流業界。ロジスティクスサービスを事業の中核として展開するセンコーグループホールディングス株式会社においても同様の課題を抱えていました。
そこで同社ではヒトの業務やノウハウをデジタル化すべく、センコー株式会社に2020年にDX推進部が発足。デジタルを用いた事業変革に取り組んでいます。
そしてこの度、Kaizen PlatformではDXコンサルティングの一環として、社内大学であるセンコーユニバーシティとセンコー㈱DX推進部とともに、DX人材育成のためのワークショップの企画・実行を支援させていただきました。
今回はセンコーユニバーシティ部長 南里様、DX推進部 部長 吉田様、そしてワークショップに参加された畑様、段坂様に、取り組みの背景から実際にワークショップを受講してみての感想や気づき、また今後の展望について伺いました。

(左から)
センコーグループホールディングス株式会社 人材教育部 センコーユニバーシティ 部長
南里 健太郎 氏
センコー株式会社 経営管理部 経営企画グループ長 畑 博文 氏
センコー株式会社 東京主管支店 立川営業所 所長 段坂 直樹 氏
センコー株式会社 事業政策推進本部 DX推進部 部長 吉田 聡 氏
物流業界の人手不足が大きな課題。デジタルを手法とした根本的改革を推し進める人材を創出するために
―― あらためてセンコーユニバーシティおよびDX推進部について、また今回の取り組みに至った背景を教えて下さい。
南里:センコーユニバーシティは、2016年に開学した社内大学でして、最先端のナレッジとスキルを有する人材の輩出、グループ全体の強化、学習する風土の醸成を目的としています。
そしてセンコーユニバーシティでは、学んで終わりではなく、学んだことをビジネスの現場で実践するということを大切にしています。そこでアクションラーニングの形式で、経営の基礎となる考え方を学びつつ、自部署や会社全体の課題に対してどう革新していくかを考え、実際の職場の中で実践していくという進め方をしてきました。
しかし昨今は変化のスピードがとても早く、さらにコロナ禍となり、もう少し遠い未来のことだと思っていたテレワークもいまや当たり前になったりと、ビジネスを進めていく前提条件が大きく変わってしまったわけです。
そしてこの先も目まぐるしく変化が訪れるわけですから、変化を当たり前と捉え、正解がわからない中で、自ら問いを立てて答えを出していく行動が求められます。
そこでセンコーユニバーシティ自体も今まで通りの企画ではなく、より学びを実践に変えていくアプローチが必要であり、特にデジタルやDX領域の人材育成は急務であると感じていたため、今回DX推進部と協働でワークショップを実施するに至りました。

人材教育部 センコーユニバーシティ 部長 南里 健太郎 氏(写真右)
吉田:やはり昨今は物流業界における労働力不足というのが社会問題化しており、当社としてもヒトに頼るビジネスモデルを長年続けてきたわけですが、ECの普及などによる物流の必要性が年々高まる一方で、ビジネスの根幹を揺るがす人手不足にどう対処するかが課題としてありました。
そうした課題解決のために、ヒトの業務やノウハウのデジタル化といったことをリードしていくべく、2020年に新設されたのがDX推進部です。
では、あらためてDXとは何かと考えたときに、ロボットの導入やシステム化を進めるといったことがDXなのではなく、デジタルを手法として、根本的な変革、改革を行うヒトを生み出すことがDXではないかと思いました。
そこで、もともとセンコーは教育に力を入れている会社のため、DX推進部とセンコーユニバーシティが一緒になって取り組みを行い、DX人材の育成をやるべきだろうと考えました。
しかし、DX領域における知見が十分にあるわけではなかったため、外部のパートナーを交えて取り組みを進めていくべきだということから、今回Kaizen Platformにコンサルティングをご相談させていただきました。

事業政策推進本部 DX推進部 部長 吉田 聡 氏(写真中央)
―― 様々な企業がある中で、Kaizen Platformに依頼しようと思ったキッカケや最終的な決め手はなんでしたか?
吉田:DX関連の情報収集を進めていく中で、Kaizen Platform代表の須藤さんの著書(『90日で成果をだす DX入門』 日本経済新聞出版社)を読み、そこに書かれていたKaizen Platformの考えに共感したことがキッカケです。
書籍はもちろん、様々な企業の講演にも参加していたのですが、須藤さんの本にはいわゆるロボットやデータ云々のことだけでなく、ヒトに着目した価値創造について書かれていて、まさにセンコーが目指している世界観と同じだと感じました。
南里:また、書籍には「計画を立て、小さく進めて、素早くアクションを起こし、小さな成功を積み上げていく」といったアプローチについて書かれていたのですが、もともと現場での改善を大切にしてきたセンコーグループのDNAと重なる部分が多くあるなと感じました。
そうした小さな一歩を大事にする会社に協力いただきたいと考えていましたから、今後DXを展開していく上でもKaizen Platformの考え方は弊社にフィットすると思いました。
そして実際にお打ち合わせをさせていただいたときも、他社はデジタル寄りの話が中心であったり、概論や総論が多かったのに対し、Kaizen Platformの場合は具体的で、学びをどう実践に繋げていくかが非常にイメージしやすく、安心できたことが最終的な依頼の決め手でした。
客観的な視点を持ち合わせながら、パートナーとして伴走いただくことに期待していた
―― あらためて、どういったワークショップであったのかご説明をお願いします。
南里:ワークショップは0期、そして1期の2回に分けて実施しました。0期のワークショップはトライアルでの実施で、DX推進部の関係者が中心となり、「顧客への価値提供」をテーマとして最終的なアウトプットを目指した対話型で進めていきました。
そして1期目では「顧客への価値提供」だけでなく、「業務プロセスの課題発見・解決」もテーマに加え、自主的なディスカッションが生まれるよう、4ヶ月で全5回とインターバルを設けての展開でした。
これらのワークショップは、DX推進の担い手の創出だけでなく、学習する風土の醸成も目的としていたので、本日同席をしている畑、段坂含めた0期のメンバーが1期ではファシリテーターとして参画するという形で実施しました。
DX領域の知見はKaizen Platformからいただきつつ、学習経験者が社内に教え伝えることで、ワークショップを自主運営できる体制を目指して進めてきました。
またワークショップではディスカッションを通じて、最終的には課題解決のための実践プランにまとめる形で進めていき、実際にデジタルを活用してどう事業課題を解決していくか、学びを実践に変えていくアクションへと繋げていきました。

―― 今回ご依頼いただくにあたり、どういったことをKaizen Platformに期待していましたか?
南里:今回ワークショップの内容を一緒に企画いただきましたが、事前のお打ち合わせのときから「そもそも、何を目的としているのか」「ユーザーはそうしたことを求めているのか」などと、本質的な問いをいただく場面が多くありました。
我々がワークショップを企画するときは、ついつい手段にフォーカスしてしまい、本質的なことを見失ってしまいかねません。しかしKaizen Platformがプロジェクトに加わり、客観的に弊社を見ていただくことで、「そもそも自分たちは何のために、何をすべきか?」といった本質に迫る考え、行動に繋がるキッカケが得られるだろうと期待していました。
吉田:また、DXを推進していく上で、自社内では「こう進めるべき」という明確な答えがない状態でしたから、その答えを一緒に探してくれる、パートナーとして伴走していただくことにも期待していました。
研修後も見据えた内容だからこそ、学んで終わりではなく、実際のアクションに繋がる企画が生まれた
―― 畑さま、段坂さまは実際にワークショップを受講してみて、いかがでしたか?
畑:これまでも社内の階層別研修や外部の研修など様々な研修を受けてきましたが、その時々で宿題があったりしても、研修が終わった後に継続して何かに取り組むといったことはなかなかありませんでした。
どうしても学んで終わりになってしまっていましたし、受講した後が大切だとわかっていても、そこに取り組む研修というのがなかったと感じています。
しかし今回は研修後の伴走も見据えた内容で、実際のアクションに結びつく企画が生まれました。センコーが抱える経営課題の解決に向けた、重要な位置づけである研修がスタートしたと実感しています。
段坂:私自身は2016年からデータサイエンス領域の取り組みを行なっていたため、正直いまさらDXのワークショップを受講する必要はないと思っていました。そのため、当初は「何か新しいアイデアの着想を得られれば十分」くらいのモチベーションだったんですね。
しかし実際に受講してみると、Kaizen Platform側から本質的なフィードバックをいただけたこと自体に大きな価値があるなと感じました。やはり自分たちだけで考えてしまうと、ときに的外れなアイデアになってしまいかねません。
自分たちが考えていることが本当にビジネスとして価値があるのかどうかを、あらためて客観的に見つめ直す非常に良い機会になりましたし、シンプルに楽しかったなと思っています。

東京主管支店 立川営業所 所長 段坂 直樹 氏
―― その他、今回のワークショップを通じての新たな気づきは何かありましたか?
畑:社員それぞれが日々の業務の中で課題に感じていることがあるのに対し、現場では文句を言って終わりで、そのような課題を経営層に伝わる形で可視化出来ていませんでした、今回のワークショップを通じてそうした課題を再認識して可視化するといったプロセスが意外とこれまではなかったのだと気づきました。
そして、今回の取り組みではリーダー層のメンバーも参加したことで、現場メンバーしか気づいていない課題などを共有する場になり、企業として自社の抱える課題を見える化できる、自社の課題の宝庫となるプロジェクトであったと感じています。

経営管理部 経営企画グループ長 畑 博文 氏
南里:DXと聞くと、 “テクニカルな魔法の杖” といった認識を持ってしまいがちですが、実際にDXを進めていくためには、自分たちの課題は何かを考え、課題解決のためのアウトプットを考えていくということが非常に大切です。
そのため畑からもあった通り、今回のワークショップは自社の課題発見、そして解決の学びに繋がるものだったと感じています。
また、今回のワークショップはすべてオンラインでの実施でした。当初はオンラインでの進行で大丈夫なのだろうかと不安でしたが、当初ネガティブなモチベーションで参加していたメンバーが徐々にポジティブになり、前向きに参加していく様子が画面越しにも伝わってくるほど、全員が当事者意識を持ち、やる気に満ち溢れているのが見れたのは期待以上でした。
DX人材教育の成果は長いスパンで見る必要がある。今回のワークショップの実施自体が自社にとっての変革だった
―― ワークショップ実施を経て、社内から何か反響はありましたか?
吉田:正直、賛否両論ありました。というのも、DX人材教育というのは半年そこらで具体的な成果が出るものではないため、その価値が見えづらいものだと思います。
しかし、自分たちの仕事の顧客価値は何か、社会価値は何かといった議論は日々の業務ではなかなか出てこないわけですが、そうしたことをワークショップを通じて悩んだり学んだりした経験は、5年、10年といった長い期間で見たときに意味があるものだと思っています。
そのため目先の成果にとらわれず、様々なご指摘を受け止めながら、受講生の成長のみを願い長期的な成果に期待しています。
畑:吉田からもありましたが、「このワークショップにどんな意味があるのか?」と懐疑的な人もいました。しかし、私はこうしたアウトプットにまでしっかりと繋げていくワークショップをやること自体が変革だったと感じているんですね。
他の社内研修や他社の研修では、実際のアクションにまで落とし込んで企画されているものがそもそもないわけで、今回トライアルとして実施しただけでも成果だと思っています。
段坂:今回、私は毎回自席からワークショップに参加していまして、社外の方と勉強している様子をあえてまわりの部下に見えるようにしていました。
というのも、変化の激しい時代において学び続けることは必須であるわけで、部下に学ぶことの必要性を説くのであれば、まず上司自身が学んでいる姿を見せるべきだと思うんですね。
今回、そうした姿勢を部下に見せれたというだけでも、組織にとって良いことだったと思っています。

―― 最後にあらためて今回の感想と、今後学びを実践に結びつけていくためのアクションとして、どういった展望を描かれているのか教えて下さい。
吉田:一緒に伴走してほしいという期待があった中で、我々の課題の背景までしっかりと考えていただけたり、実際に研修後も伴走していただけたりと、とても期待以上でした。
そして今後は学びのための学びではなく、コミュニティとしてどう機能させていくかが重要であると考えています。そのため、ワークショップで生まれたビジネスの種を放置することなく、しっかりと履歴として閲覧できる形に残し、その時々の技術を掛け合わせるなどして実現できるようなコミュニティを形成していきたいと考えています。
南里:将来、教科書に載るような激動の時代の中、Kaizen Platformはテクノロジー含め情報感度の高い企業であり、時代の流れを読む上で求められる情報を客観的に提供していただけていることに感謝しています。
そしてセンコーグループの社員かと勘違いしてしまうくらい、我々の事業に寄り添い、パートナーとして取り組んでくださっていることが本当に期待以上でした。
今後はより学びを実践に変えていくためのコースを強化していきたいと考えており、また受講生や卒業生が集まり、議論できる場所をつくっていきたいと考えています。そうした実践フェーズでの取り組みもKaizen Platformと一緒に進めていきたいと考えているため、引き続きどうぞよろしくお願いいたします!
<取材・執筆・撮影:永田 優介/編集:Kaizen 編集部>